中古工作機械の選定は、まるで地雷原を歩くようなもの。目の前に転がる「格安」という名の魅力的な果実に手を伸ばした瞬間、足元で時限爆弾が作動する…そんな悪夢を、あなたは心のどこかで恐れていませんか?「コストは抑えたい、でも安物買いの銭失いは絶対に嫌だ」。そのジレンマは、設備投資という重大な決断を担うあなたにとって、あまりにも重い十字架でしょう。多くの人が「とりあえず動けばいい」というギャンブルに身を投じ、結果として修理費と機会損失という名の泥沼に沈んでいく現実を、私たちはもう見過ごすわけにはいきません。
ご安心ください。この記事は、そんなあなたのための「地雷探知機」であり、安全なルートを指し示す「精密な地図」です。この記事を最後まで読んだとき、あなたは中古工作機械を単なる「鉄の塊」としてではなく、将来にわたって利益を生み出す「戦略的資産」として見抜く、鋭い鑑定眼を手にしていることでしょう。価格という一点の曇ったレンズを通して世界を見るのをやめ、その機械が持つ過去の歴史、現在の健康状態、そして未来の可能性という、三つの時間軸を貫くクリアな視点を提供します。もう、販売業者の甘い言葉や、見た目の綺麗さに惑わされることはありません。あなたの工場にとって、本当の意味で「儲かる機械」を選び抜くための、論理的かつ実践的な知見が、ここにあります。
| この記事で解決できること | この記事が提供する答え |
|---|---|
| 価格の安さに潜む「本当のコスト」を見抜くにはどうすればいい? | 購入後の修理費や電気代まで含めた「総所有コスト(TCO)」で判断する視点と、機械の心臓部である主軸・ボールねじ・電気系統の健全性を見抜くプロのチェック術。 |
| 将来も安心して使える「価値ある中古」と「すぐ壊れるゴミ」の決定的な違いは? | 将来のIoT化や自動化に対応できる「未来価値(レトロフィットの可能性)」と、10年後も部品に困らない「供給の継続性」という、他にはない本質的な選定基準。 |
| 悪質な業者を避け、信頼できる販売パートナーを確実に見つける方法は? | 整備履歴の開示要求や保証内容の確認はもちろん、「この質問をすればプロとわかる」具体的なヒアリング項目リストで、相手の誠実さと技術力を丸裸にします。 |
もはや、中古工作機械選びは運任せのギャンブルではありません。それは、知識と戦略に基づいた、知的な投資活動です。さあ、価格という名の呪縛から解き放たれ、あなたの工場に真の利益をもたらす最高の一台を見つけ出す旅を始めましょう。そのための羅針盤は、すべてこの先に記されています。
- 価格だけで判断しない!未来の利益を生む「中古工作機械 選定基準」完全ガイド
- まずは陥りがちな罠を知る:中古工作機械の選定でよくある3つの致命的ミス
- 【基礎編】プロが必ず確認する、中古工作機械の物理的健全性を見抜く選定基準
- 「誰から買うか」も重要な選定基準:信頼できる中古工作機械販売業者の見極め方
- 【本質】この記事だけの独自視点:中古工作機械の価値を最大化する「未来価値」という新・選定基準
- あなたの工場に本当にフィットする?「運用適合性」から見る中古工作機械の選定基準
- 見えないコストを可視化する:中古工作機械の「総所有コスト(TCO)」に基づく選定基準
- 失敗しない中古工作機械の選定プロセス:問い合わせから契約までの5ステップ
- 【実践ツール】抜け漏れゼロへ!戦略的「中古工作K機械 選定基準」チェックリスト
- 中古工作機械の選定後も重要!導入後の価値を最大化する運用術
- まとめ
価格だけで判断しない!未来の利益を生む「中古工作機械 選定基準」完全ガイド
新たな設備投資として中古工作機械の導入を検討する。それは、多くの製造業にとって、コストを抑えつつ生産能力を向上させるための賢明な選択肢となり得ます。しかし、その選定プロセスは、まるで宝探しにも似た難しさを伴うもの。価格という一点のみに光を当ててしまうと、その影に潜む大きなリスクを見落とし、結果として未来の利益を損なう「安物買いの銭失い」に陥ってしまうのです。
中古工作機械の選定は、単なる「買い物」ではありません。それは、自社の未来を左右する「戦略的投資」に他ならないのです。この一台が、これから先の5年、10年、あなたの工場の生産性を支え、利益を生み出す源泉となる。その可能性を秘めているからこそ、私たちは慎重かつ多角的な視点を持つ必要があります。目先の価格だけでなく、その機械が持つ真の価値を見抜くための確かな羅針盤。それが、本記事で提供する「中古工作機械 選定基準」です。
本稿を最後までお読みいただくことで、あなたは単なるチェックリストを超え、自社の事業戦略と深く結びついた、後悔のない中古工作機械選定を実現するための知見を得ることができるでしょう。さあ、未来の利益を共に育む、最高の一台を見つけ出す旅を始めましょう。
なぜ、多くの企業が中古工作機械の選定で失敗してしまうのか?
「とりあえず動けばいい」「とにかく安いものを」。こうした考えが、中古工作機械選定における失敗の序章となることは、決して少なくありません。多くの企業が陥る失敗の本質は、工作機械というものを「単なる鉄の塊」として捉え、その裏側にある時間経過による劣化や、自社の生産目的との適合性といった、目に見えない価値を見過ごしてしまう点にあります。
例えば、購入後すぐに頻発する故障。予期せぬ修理費用と、生産がストップする機会損失は、当初抑えたはずの導入コストを瞬く間に上回ります。また、オーバースペックな機械を導入してしまい、その性能を全く活かせずに持て余すケースや、逆にスペック不足で求める加工品質が出せず、不良品の山を築いてしまう悲劇も後を絶ちません。これらは全て、表面的な情報だけで判断を下した結果なのです。
失敗の根本原因は、中古工作機械が持つ「過去(使用履歴やメンテナンス状況)」と「未来(将来の拡張性や耐久性)」を正しく評価せず、「現在(見た目や価格)」だけで判断してしまうことに集約されます。この時間軸の欠如こそが、多くの企業を後悔へと導くのです。
本記事が提供する、単なるチェックリストを超えた「戦略的選定」という新たな視点
市場には中古工作機械に関する情報が溢れていますが、その多くは「主軸の振れを確認する」「摺動面の傷を見る」といった、断片的なチェック項目を羅列するに留まります。もちろん、それらは重要な選定基準の一部ですが、森を見ずに木を見ているに過ぎません。本記事が提唱するのは、それらを包括し、さらにその先を見据えた「戦略的選定」という新たな視点です。
「戦略的選定」とは、その中古工作機械が、あなたの会社の事業戦略、財務計画、そして未来の成長にどう貢献するのか、という経営的視点から選定を行うアプローチのことを指します。それは、単に「使える機械」を探すのではなく、「儲かる機械」「会社を強くする機械」を見つけ出すための思考法。具体的には、目先の価格だけでなく総所有コスト(TCO)を算出し、将来的なIoT化や自動化への対応可能性(未来価値)を評価し、現場の運用フローに本当に適合するのか(運用適合性)を徹底的に検証します。
私たちは、単なる機械の良し悪しを判断するチェックリストではなく、あなたの会社に持続的な競争力と利益をもたらすための「思考のフレームワーク」を提供します。この視点を持つことで、中古工作機械の選定は、リスクを伴う賭けから、確信に満ちた戦略的投資へと昇華するのです。
まずは陥りがちな罠を知る:中古工作機械の選定でよくある3つの致命的ミス
成功への道筋を描く前に、まずは多くの人が足を取られる落とし穴の存在を知っておく必要があります。中古工作機械の選定において、知識や経験が浅い場合に特に陥りやすい、致命的とも言える3つのミスが存在します。これらは一見、些細な判断ミスに見えるかもしれませんが、導入後の生産性や収益性に深刻なダメージを与えかねない、まさに「罠」なのです。
これらのミスは、いずれも表面的な情報に惑わされ、その裏に潜む本質的なリスクを見過ごしてしまう点に共通しています。これから挙げる3つのミスを事前に理解し、自社の選定プロセスにおいて常に意識することで、失敗の確率を劇的に下げることができるでしょう。以下の表で、それぞれのミスの概要と、それがもたらす悲惨な結末を確認してください。
| 致命的ミス | 概要 | もたらされる最悪の結果 |
|---|---|---|
| ミス1:価格至上主義 | 本体価格の安さだけを絶対的な選定基準とし、購入後のコストを一切考慮しない。 | 修理・部品交換費、低い生産性による機会損失などが嵩み、新品購入よりも総コストが高くつく。 |
| ミス2:スペック至上主義 | 自社の加工目的を深く分析せず、カタログ上の高性能・高機能なスペックに惹かれて選んでしまう。 | オーバースペックで宝の持ち腐れになる、またはスペック不足で不良品を量産し、顧客の信頼を失う。 |
| ミス3:「現状品」過信 | 「現状動作品」という言葉を「問題なく使える」と解釈し、詳細な状態確認を怠る。 | 導入直後から頻繁な故障や精度不良に見舞われ、生産計画が完全に破綻する。 |
これらのミスを回避する第一歩は、「中古工作機械は一台一台すべて状態が異なる一点物である」という大原則を心に刻むことです。この認識こそが、表面的な魅力に惑わされず、機械の本質的な価値を見抜くための出発点となります。
ミス1:目先の安さだけで判断し、隠れたランニングコストを見逃す
中古工作機械選定における最も古典的かつ、最も多くの企業が陥る罠。それが、初期投資額である本体価格の安さだけで判断を下してしまうことです。「新品の半額以下だ!」という魅力的な数字は、冷静な判断力をいとも簡単に曇らせます。しかし、工作機械の本当のコストは、購入した瞬間に終わりではありません。むしろ、工場に設置され、電源が入ったその日から、本当のコスト計算が始まるのです。
格安で手に入れた機械が、実は電気代を大量に消費する旧式のモーターを搭載していたら? 主要な消耗部品が既に寿命寸前で、導入後すぐに高額な交換費用が発生したら? あるいは、度重なるマイナートラブルで生産ラインが頻繁に停止し、納期遅延という最悪の事態を招いてしまったら? これら全てが「隠れたランニングコスト」です。本体価格という氷山の一角だけを見て、その水面下に広がる巨大なランニングコストという氷山本体を見逃すことが、このミスの本質と言えるでしょう。
ミス2:スペック至上主義に陥り、自社の加工目的とのミスマッチを招く
カタログに並ぶ華々しい数値。最大回転数、早送り速度、搭載されている機能の数々。技術者であればあるほど、こうした「スペック」の高さに心惹かれるのは自然なことかもしれません。しかし、そのスペックは本当にあなたの工場で必要とされているものでしょうか。スペック至上主義とは、自社の「目的」を深く見つめることなく、「性能」という名の幻想を追い求めてしまう罠です。
例えば、±10ミクロンの公差で十分な部品を加工する工場が、サブミクロン単位の超高精度マシニングセンタを導入したとします。これは明らかにオーバースペックであり、その性能を活かす機会は永遠に訪れないかもしれません。投資コストが無駄になるだけでなく、複雑な操作やメンテナンスが現場の負担を増やす結果にもなり得ます。逆に、精密部品の受注を目指しているにも関わらず、要求精度を満たせない機械を選んでしまえば、それは単なる鉄の塊と化します。
最も重要な選定基準は「その機械で何を作るのか」という原点であり、スペックはその目的を達成するための手段に過ぎません。この主従関係を見誤ることが、致命的なミスマッチを招くのです。
ミス3:「現状動作品」という言葉を鵜呑みにし、将来の故障リスクを軽視する
中古市場で頻繁に目にする「現状動作品」や「通電確認済み」という魔法の言葉。この言葉は、一見すると安心材料のように響きますが、実は非常に大きなリスクを内包しています。なぜなら、「動く」ことと、「要求される精度で、安定して生産し続けられる」ことは、全くの別次元の話だからです。エンジンがかかるからといって、その車で安心して長距離レースに挑めないのと同じ理屈です。
電源が入り、主軸が回転し、テーブルが動く。それは最低限のスタートラインに過ぎません。その裏側では、目に見えない摩耗が進行しているかもしれません。主軸内部のベアリング、精度を司るボールねじ、長年の稼働で劣化した電気部品や制御装置(CNC)。これらの時限爆弾は、購入時点では静かに眠っていても、あなたの工場で本格稼働を始めた途端に牙を剥き、高額な修理費用と貴重な生産時間を奪い去ります。
「現状動作品」という言葉は、あくまで「現時点での最低限の動作保証」に過ぎず、将来にわたる安定稼働や加工精度を何ら保証するものではない、と理解することが極めて重要です。この言葉の裏に潜むリスクを正しく評価できるかどうかが、プロとアマチュアを分ける分岐点となります。
【基礎編】プロが必ず確認する、中古工作機械の物理的健全性を見抜く選定基準
「現状動作品」という言葉の甘い響きの裏に潜むリスクを回避するためには、我々自身が機械の健康状態を診断する「目」を持たねばなりません。ここからは、プロの技術者が実機確認で必ずチェックする、中古工作機械の物理的な健全性を見抜くための具体的な選定基準について、その核心に迫ります。外観の塗装や清掃状態に惑わされてはいけません。本当に見るべきは、長年の稼働によって確実に消耗・劣化していく機械の心臓部や骨格です。この物理的な健全性を見極める能力こそ、あなたの重要な投資を失敗から守るための、最も基礎的かつ強力な盾となるのです。この章で挙げるポイントは、後悔しない中古工作機械選定における、いわば必須科目と言えるでしょう。
精度を左右する心臓部:主軸(スピンドル)の振れ・異音・発熱の確認方法
工作機械の心臓部、それが主軸(スピンドル)です。製品の加工精度を最終的に決定づける、まさに最重要部品。この主軸の状態を見誤ることは、中古工作機械の選定において致命的な失敗を意味します。確認すべきは「振れ」「異音」「発熱」の三点。これらは主軸内部に組み込まれたベアリングが健康か、あるいはすでに悲鳴を上げているかを示す動かぬ証拠なのです。ダイヤルゲージを当てて主軸の振れを測定し、規定値内に収まっているかを確認するのは基本中の基本。さらに、静かな環境で低速から高速まで回転させ、「ゴロゴロ」「キーキー」といった異音がないか、耳を澄ませてください。そして、一定時間(最低でも30分程度)の慣らし運転後、主軸周辺が異常に熱を持っていないかを手で触れて確認することも、ベアリングの寿命を推し量る上で欠かせない重要な選定基準です。これらを怠ることは、時限爆弾を工場に迎え入れることに他なりません。
消耗と劣化のサインはどこに出る?ボールねじ・スライド摺動面の摩耗度チェック
主軸が精度を司る心臓ならば、ボールねじやスライド摺動面は、その動きを正確に伝える骨格であり、神経網と言えるでしょう。テーブルや刃物台を滑らかに、そして正確に位置決めするこれらの部品の摩耗は、加工寸法のばらつきや、真円加工が楕円になるなどの形状不良に直結します。ボールねじの摩耗は、ハンドルを手で回した際の「バックラッシ(遊び)」の大きさで体感できます。この遊びが大きい機械は、正確な位置決めが困難になっている証拠。また、スライド摺動面は、潤滑油が適切に行き渡っているか、深い傷や「カジリ」と呼ばれる引きずり痕がないかを目視で厳しくチェックする必要があります。見た目の綺麗さに惑わされず、機械の動作の根幹を支えるこれらの部分に潜む消耗と劣化のサインを読み取ることこそ、プロが実践する中古工作機械の選定基準なのです。
電気系統と制御装置(CNC):中古工作機械で最もトラブルが多い部分の選定ポイント
機械の体躯がいかに屈強でも、それを制御する頭脳と神経、すなわち電気系統と制御装置(CNC)が不調では話になりません。驚くべきことに、中古工作機械において最もトラブルが発生しやすく、かつ修理費用が高額になりがちなのがこの電気系統なのです。見過ごされがちな制御盤の内部や、日々操作するボタンの反応一つ一つに、将来の大きなリスクが隠されています。実機確認の際は、必ず制御盤の扉を開けてください。ホコリや油で汚れた盤内、硬化してひび割れた配線、異音を発する冷却ファン。これらは全て、いつ重大な故障を引き起こしてもおかしくない危険信号です。以下の表は、この重要な部分を見極めるための具体的な選定ポイントをまとめたものです。
| 確認箇所 | チェックポイント | この確認がなぜ重要なのか |
|---|---|---|
| 制御盤(キャビネット)内部 | ・内部の清掃状態(ホコリ、油汚れ、湿気) ・冷却ファンの正常な動作と異音の有無 ・配線の状態(硬化、ひび割れ、結束の乱れ) | 盤内の汚損や冷却不良は、電子部品のショートやオーバーヒートによる突然の機械停止に直結する。 |
| 制御装置(CNC)本体 | ・ディスプレイの表示状態(焼き付き、チラつき) ・操作パネルのボタンやスイッチの反応(鈍さ、無反応) ・メーカー名と型式(古すぎないか) | 表示や操作の不具合は作業効率を著しく低下させる。旧式のCNCは修理部品の入手が絶望的で、故障=廃却となるリスクを孕む。 |
| モーター類 | ・主軸モーター、サーボモーターの異音や異常な振動 ・稼働中の発熱状態 | モーターの不具合は加工品質の低下や位置決め不良の直接的な原因となり、交換には高額な費用がかかる。 |
| 各種センサー・リミットスイッチ | ・正常に反応するか ・油や切りくずで汚れていないか | センサー類の不調は、誤動作や衝突事故の原因となり、機械全体に深刻なダメージを与える可能性がある。 |
「誰から買うか」も重要な選定基準:信頼できる中古工作機械販売業者の見極め方
ここまで、機械そのものの物理的な状態を見抜くための選定基準を詳細に解説してきました。しかし、忘れてはならない事実があります。それは、これら専門的な項目を、購入者が独力で、しかも限られた時間内に完璧に評価するのは至難の業だということ。そこで浮上するのが、もう一つの極めて重要な選定基準です。それは「何を」買うかだけでなく、「誰から」買うかという視点。信頼できる販売業者というパートナーを見つけ出すことこそ、中古工作機械選びという航海の成功確率を飛躍的に高める、最も賢明な羅針盤なのです。機械の状態をごまかさず、購入後のリスクまで誠実に説明してくれる業者か、それとも売りっぱなしで終わらせる業者か。その差は、あなたの事業の未来を大きく左右します。
保証とアフターサポートの有無は、将来の安心を左右する選定基準
「現状渡し、ノークレーム・ノーリターン」。中古工作機械の取引でしばしば目にするこの言葉は、販売者側が購入後の機械に一切の責任を負わないという宣言に他なりません。一方で、真に信頼できる業者は、自社が販売する機械に自信と責任を持つ証として、手厚い保証やアフターサポート体制を整えています。この差は、万が一購入後に問題が発生した際の安心感において、まさに天と地ほどの違いを生むでしょう。目先の数万円、数十万円の価格差以上に、この「見えない保険」の価値を正しく評価することが、長期的な視点に立った賢い中古工作機械の選定基準と言えます。保証やサポートの有無は、単なる付加価値ではなく、その販売業者の誠実さと技術力を測るバロメーターなのです。購入を検討する際には、以下の点を確認することが不可欠です。
- 保証の期間と範囲:保証期間はどれくらいか。保証されるのは部品代のみか、それとも出張費や作業費まで含まれるのか。
- トラブル発生時の対応体制:電話での技術的な質問に答えてくれるか。故障時にどれだけ迅速に技術者を派遣してくれるのか。
- メンテナンス体制:定期的なメンテナンス契約を結ぶことは可能か。消耗部品の供給ルートを確保しているか。
- 専門知識と実績:その機械のメーカーや機種に精通しているか。納入や修理の実績は豊富か。
過去のメンテナンス履歴(整備記録)の開示を求める重要性とは?
もし、あなたが中古車を購入するならば、過去の点検整備記録簿の有無を気にするのではないでしょうか。中古工作機械の選定も、これと全く同じです。過去のメンテナンス履歴(整備記録)は、その機械が前のオーナーにどのように扱われ、どのような歴史を辿ってきたかを雄弁に物語る「カルテ」そのもの。このカルテの開示を求める行為は、機械の隠れた状態を深く知るためだけでなく、販売業者の透明性と誠実さを測るための、非常に有効なリトマス試験紙となるのです。定期的な点検やオイル交換が実施されてきたか、過去に重大な故障や部品交換はあったか。これらの情報は、将来の故障リスクを予測し、適切なメンテナンス計画を立てる上で計り知れない価値を持ちます。メンテナンス履歴の開示を快く受け入れる業者は、自社の商品知識に自信があり、顧客と誠実な関係を築こうとしている証拠に他なりません。逆に開示を渋ったり、「ない」の一言で済ませたりする業者は、何かを隠している可能性を疑ってかかるべきでしょう。
【本質】この記事だけの独自視点:中古工作機械の価値を最大化する「未来価値」という新・選定基準
これまでの選定基準が、機械の「過去」と「現在」の状態を正しく評価するためのものだったとすれば、ここからお話しするのは、その機械が持つ「未来」への投資価値を見極めるための、全く新しい視点です。物理的な健全性や販売業者の信頼性はもちろん重要。しかし、真に戦略的な投資とは、購入する資産が将来にわたって価値を増大させる可能性を秘めているか否かを見抜くこと。それこそが、本記事が提唱する「未来価値」という、他にはない中古工作機械の選定基準なのです。
あなたが今、目の前にしているその一台は、単なる減価償却資産ではなく、未来の製造業の激変に対応し、新たな利益を生み出す「種」となり得るのか。この問いこそが、中古工作機械の選定を単なるコスト削減策から、積極的な未来への投資へと昇華させる鍵となります。価格や現状のスペックだけでは決して測れない、その機械に眠るポテンシャル。それを評価する思考のフレームワークが、ここにあります。
「レトロフィット」の可能性:その中古工作機械は将来のIoT化や自動化に対応できるか?
時代は、インダストリー4.0の潮流の中、IoTによる「見える化」やロボットによる「自動化」へと突き進んでいます。このような未来を見据えた時、あなたが選ぶ中古工作機械は、単に今日の仕事をこなすだけの存在であってはなりません。「レトロフィット」という言葉をご存知でしょうか。これは、既存の古い機械に最新のCNC装置やセンサー、ロボットインターフェースなどを後付けし、性能や機能を劇的に向上させる技術のこと。このレトロフィットの可能性こそ、「未来価値」を測る重要な選定基準なのです。
選定の際に問うべきは、「この機械の基礎体力は、将来の頭脳(制御装置)や神経(センサー)の進化に耐えうるか?」という点です。例えば、鋳物でできた本体(ベッドやコラム)の剛性が非常に高い旧式の機械は、まさにレトロフィットの絶好の素体。最新の制御装置を載せ替えることで、現行機に匹敵する、あるいはそれ以上の生産性を発揮する可能性すら秘めています。機械本体の基本的な構造や剛性といった「変えられない部分」の素性が良い機械を選ぶこと、それが将来のIoT化や自動化という拡張性を担保し、長期的な投資価値を最大化させるための本質的な中古工作機械の選定基準と言えるでしょう。
部品供給の継続性:10年後も安心して使えるかを見極めるための選定基準
どれほど頑丈で、未来価値を秘めた中古工作機械を手に入れたとしても、たった一つの部品が手に入らないだけで、それは巨大な文鎮と化してしまいます。中古工作機械の選定における最大のリスク、それは「部品供給の打ち切り」に他なりません。特に、制御装置(CNC)やモーター、特殊なセンサーといった電気系統の部品は、モデルチェンジのサイクルが早く、10年も経てば入手が絶望的になるケースも珍しくありません。このリスクを正しく評価することこそ、未来の安定稼働を約束する上で欠かせない選定基準です。
確認すべきは、まず機械メーカーとCNCメーカーが現存し、安定した経営を続けているか。そして、その機種が市場でどれだけ普及したモデルであるか。ベストセラー機であればあるほど、メーカー純正品だけでなく、サードパーティ製の互換部品や、中古部品市場での流通も期待できます。「この機械は、10年後も修理できるのか?」という厳しい問いを販売業者に投げかけ、その返答の具体性と信憑性を吟味すること。これが、将来の稼働停止リスクをヘッジし、購入した機械を本当の意味で「自社の資産」にするための、極めて重要なプロセスなのです。
あなたの工場に本当にフィットする?「運用適合性」から見る中古工作機械の選定基準
最高性能のF1マシンも、未舗装の農道を走ることはできません。それと同じように、いかに優れたスペックを持つ中古工作機械であっても、あなたの工場の運用環境や文化に適合しなければ、その真価を発揮することは不可能なのです。これまで機械「単体」の価値を評価する選定基準について述べてきましたが、ここからは視点を変え、あなたの工場という「システム全体」にいかにフィットするか、という「運用適合性」について掘り下げていきます。
この運用適合性という選定基準は、導入後のスムーズな立ち上がり、現場の混乱の最小化、そして投資対効果の最大化に直結する、極めて実践的な評価軸です。機械を「点」としてではなく、既存の設備や人材、ワークフローといった「線」や「面」との関係性の中で捉えること。この視点を持つことで初めて、あなたの工場にとって本当に「使える」一台、すなわち真に価値ある中古工作機械の選定が実現するのです。
既存設備との連携は可能か?ツーリング・治具・プログラムの互換性を確認
新しい中古工作機械を導入した際、最も見過ごされがちで、かつ深刻な「見えないコスト」を発生させるのが、既存設備との非互換性です。特に、ツーリング(刃物を取り付けるホルダー)、ワークを固定する治具、そして機械を動かすNCプログラム。これらの互換性を事前に確認しておくことは、中古工作機械の選定において、機械本体のスペックと同等、あるいはそれ以上に重要な意味を持ちます。なぜなら、これらの非互換性は、導入後の立ち上げを大幅に遅らせ、予期せぬ追加投資を強いる直接的な原因となるからです。
例えば、ツーリングの規格が既存機と異なれば、高価なホルダーや工具を全て買い揃えなければなりません。治具の取り付けピッチや方法が違えば、一からの作り直しです。これらは、導入を決定してから発覚するのでは遅すぎます。中古工作機械の選定段階で、これらの互換性を徹底的に洗い出し、非互換な部分については事前に対策コストを見積もっておくことこそが、プロジェクト全体の予算とスケジュールを守るための、プロフェッショナルなリスク管理なのです。
| 確認項目 | 具体的なチェックポイント | なぜこの確認が重要なのか |
|---|---|---|
| ツーリングシステム | ・主軸テーパの規格(BT/BBT, HSK, CAT, NMTBなど)が既存機と共通か ・プルスタッドボルトの型式は同じか ・ATC(自動工具交換装置)のマガジンに収納できる工具径や長さに問題はないか | 規格が異なれば、既存の工具資産が全く使えず、数百万円単位の追加投資が必要になる。工具の共用化は、コスト削減と段取り時間短縮の基本である。 |
| 治具・パレット | ・テーブルのT溝のサイズやピッチは既存の治具と適合するか ・APC(自動パレット交換装置)がある場合、パレットの互換性はあるか ・油圧や空圧の取り出し口はあるか、仕様はどうか | 治具が流用できない場合、設計・製作に多大な時間とコストを要する。特に多品種少量生産の現場では、治具の標準化が生産性を大きく左右する。 |
| NCプログラム | ・CNCのメーカー(FANUC, 三菱, OKUMA等)が同じか ・Gコード/Mコード体系に特殊な仕様はないか ・既存のCAMソフトのポストプロセッサが対応しているか | プログラムの互換性がない場合、過去のプログラム資産が活用できず、全て作り直しとなる。これは膨大な工数を発生させ、品質の安定も損なうリスクがある。 |
現場の技術者が使いこなせるか?操作性とメンテナンス性の事前評価
どんなに優れた性能を持つ機械も、それを操る「人」がいなければただの鉄の塊。この自明の理は、中古工作機械の選定においてこそ、強く意識されるべきです。特に重要なのが、現場の技術者たちが持つスキルや経験と、導入する機械の操作性とのマッチング。例えば、長年ファナック製の制御装置に慣れ親しんだ現場へ、操作体系が全く異なるオークマやマザックの機械を何の説明もなく導入すれば、何が起こるでしょうか。操作ミスによる衝突事故、性能を全く引き出せない非効率な運用、そして何より、現場の技術者たちのモチベーション低下は避けられません。
選定時には、必ず現場のキーマンを実機確認に同行させるべきです。操作パネルのボタン配置は直感的か、プログラム作成や編集はしやすいか、アラーム発生時の対処は分かりやすいか。彼らの視点で評価することが不可欠。さらに、日常点検のしやすさ、すなわちメンテナンス性も忘れてはならない選定基準です。潤滑油の補給口やフィルターの清掃箇所が、カバーの奥深く、やりにくい場所にあれば、日々のメンテナンスは確実に疎かになり、機械の寿命を縮める結果を招くでしょう。
導入後の生産性をシミュレーションする:中古工作機械を選定する上での思考実験
さて、これまで様々な角度から中古工作機械の選定基準を検証してきました。物理的な健全性、未来価値、そして運用適合性。最後のステップとして、これらの評価を統合し、最終的な意思決定の精度を高めるための「思考実験」を行うことを強く推奨します。それは、単なるスペックの比較や価格の評価ではなく、「もし、この機械を我々の工場に導入したら、生産性と収益性は具体的にどう変わるのか」をシミュレーションすることです。
まず、あなたの工場で生産している代表的な製品をいくつかピックアップしてください。そして、その製品を検討中の中古工作機械で加工した場合のサイクルタイムを、概算で良いので算出してみるのです。主軸の回転数、送り速度、工具交換時間といったカタログスペックを基に、現在の加工時間と比較してみましょう。さらに、段取り替えの時間は短縮されるか、人的工数はどう変わるか、不良率は改善されそうか。この思考実験を通じて、その機械がもたらすであろう「1時間あたりの付加価値額」や「損益分岐点」を具体的にイメージすること。これこそが、感覚的な「良さそう」という評価を、経営判断に資する「数値的な根拠」へと転換させる、最も重要なプロセスなのです。
見えないコストを可視化する:中古工作機械の「総所有コスト(TCO)」に基づく選定基準
中古工作機械の選定において、その圧倒的な魅力は「価格の安さ」にあることは疑いようのない事実です。しかし、その価格という一点だけを見つめることは、巨大な氷山の一角を眺めているに過ぎません。真に賢明な投資家が見るべきは、水面下に隠された、購入後のあらゆるコストを含めた「総所有コスト(TCO:Total Cost of Ownership)」という名の氷山全体。このTCOという概念こそ、目先の安さに惑わされることなく、長期的な視点で最も経済合理性の高い一台を選び抜くための、唯一無二の羅針盤となるのです。
TCOに基づく選定基準を導入することは、中古工作機械の購入を単なる「出費」から、将来の利益を計算できる「戦略的投資」へと昇華させるための、決定的な一歩と言えるでしょう。本体価格の安さに踊らされることなく、その機械を所有し、運用し、そしていつか手放す日までにかかる全てのコストを可視化する。その先にこそ、後悔のない選定の答えが待っているのです。
本体価格+輸送費+設置費用だけではない、隠れた初期費用の算出方法
中古工作機械の導入を決意した際、多くの人が見積もるのは「本体価格」「輸送費」「設置費用」という三点セットでしょう。しかし、本当の初期費用は、それだけでは終わりません。まるで舞台の幕が開いた後に次々と現れる登場人物のように、「隠れた初期費用」があなたの予算計画を静かに、しかし確実に脅かし始めるのです。これらを事前に洗い出し、予算に組み込んでおくことは、プロジェクトの成否を分ける極めて重要な作業に他なりません。
例えば、機械の重量や求められる精度によっては、既存の床では耐えられず、数日から数週間を要する基礎工事が必要になるかもしれません。また、機械本体は安くても、効率的な運用に不可欠なミストコレクタやチップコンベアが付属しておらず、別途購入しなければならないケースも。これらの見過ごされがちなコストを事前にリストアップし、総額を把握することこそが、導入後に「こんなはずではなかった」という悪夢を避けるための、最も確実な中古工作機械の選定基準なのです。
修理費用・部品交換・電気代まで含めた長期的なランニングコストの比較
無事に設置が完了し、稼働を開始したその瞬間から、新たなコスト計算が始まります。それが、日々の生産活動に伴って発生し続ける「ランニングコスト」です。このランニングコストは、中古工作機械のTCOを考える上で、本体価格以上に大きな影響を与える要素。特に、旧式の機械やメンテナンス状態の悪い機械は、ランニングコストという名の見えない出血を続け、あなたの工場の体力を静かに奪っていくのです。
最新の省エネ機種と比較して、古い機械の電気代が年間でどれだけ高くなるか、考えたことはありますか。あるいは、いつ発生するかわからない高額な主軸ベアリングやボールねじの交換費用を、事業計画に織り込んでいるでしょうか。中古工作機械を選定する際は、新品、あるいは他の候補機と比較して、長期的なランニングコストがどうなるかを具体的に比較検討することが不可欠です。以下の表は、その比較検討に役立つ主要なランニングコスト項目です。
| ランニングコスト項目 | 具体的な内容 | なぜ中古機械で特に注意が必要か |
|---|---|---|
| 修理・メンテナンス費用 | ・定期的な点検、オーバーホール費用 ・突発的な故障に伴う修理費、技術者派遣費 | 経年劣化により、新品に比べて故障発生率が高まる傾向にある。保証がなければ全額自己負担となる。 |
| 消耗・交換部品費用 | ・主軸ベアリング、ボールねじ、各種モーター ・油圧・空圧機器、センサー、ケーブル類 | 各部品には寿命があり、交換には高額な費用がかかる。旧式モデルでは部品の入手自体が困難な場合もある。 |
| 光熱費(主に電気代) | ・主軸モーター、サーボモーター、油圧ユニット等の消費電力 | 古い機械は省エネ設計がされておらず、最新機種に比べて消費電力が格段に大きい場合が多い。 |
| その他(オイル・消耗品) | ・潤滑油、作動油、クーラント液、各種フィルター | 機械によっては特殊なオイルが必要であったり、オイル漏れによって消費量が想定以上になったりすることがある。 |
TCOで比較して初めてわかる、新品購入 vs 中古工作機械選定の損益分岐点
初期費用とランニングコスト。この二つの要素が出揃った時、私たちは初めて、中古工作機械の本当の価値を測るための土台に立つことができます。ここで用いるべき究極の選定基準が、TCO(総所有コスト)の概念を用いた、新品購入との損益分岐点のシミュレーションです。これは、単なる感覚的な比較ではなく、具体的な数字に基づいた、極めて論理的な意思決定プロセスに他なりません。
計算はシンプルです。まず、新品と中古、それぞれの「初期費用総額」を算出します。次に、それぞれの「年間ランニングコスト」を予測し、その差額を計算します。そして、初期費用の差額を、年間のランニングコスト差額で割る。そうして導き出された年数が、損益分岐点です。この年数を超えると、初期費用が安かったはずの中古工作機械の方が、総所有コストでは新品を上回ってしまうのです。TCOという共通の物差しで比較して初めて、「何年使えば元が取れるのか」そして「何年目から損をするのか」という、投資の本質が見えてくるのです。この損益分岐点を把握することこそ、価格という幻想から目を覚まし、自社にとって最も利益をもたらす選択を行うための鍵となります。
失敗しない中古工作機械の選定プロセス:問い合わせから契約までの5ステップ
これまで、中古工作機械を選定するための様々な基準、「物理的健全性」から「未来価値」、そして「TCO」に至るまでを多角的に解説してきました。しかし、これらの知識も、実際の行動に移せなければ宝の持ち腐れ。ここからは、その知識を武器に、失敗という荒波を乗り越えて理想の一台に辿り着くための具体的な航海術、すなわち「問い合わせから契約までの5ステップ」を解説します。
闇雲に販売業者へ電話をかける前に、この体系立てられたプロセスを踏むことが、結果的に時間とコストを節約し、致命的なミスを防ぐ最善の策となるのです。このプロセスは、あなたの会社にとって最適な一台を見つけ出すための、確かな道標。さあ、後悔のない選定に向けた、具体的な一歩を踏み出しましょう。
ステップ1:要求仕様書の作成 – 「何となく」の選定を防ぐための必須作業
中古工作機械の選定における全ての失敗は、「何となく」から始まると言っても過言ではありません。「何となく良さそう」「何となく安かったから」。そんな曖昧な動機が、導入後のミスマッチや予期せぬコストという悲劇を生むのです。その「何となく」を排除し、選定に揺るぎない軸を与えるための最初の、そして最も重要なステップが「要求仕様書」の作成です。これは、あなたの会社が機械に何を求めているのかを明確に定義した、いわば機械探しの設計図に他なりません。
この設計図があることで、あなたは無数の選択肢の中から自社に必要な機械だけを効率的に絞り込むことができ、販売業者との交渉においても明確な基準を持って臨むことができます。この要求仕様書の作成という地道な作業こそが、中古工作機械選定というプロジェクト全体の質を決定づける、まさに礎となるのです。以下の表を参考に、自社だけの仕様書を作成してみてください。
| 分類 | 要求仕様書の項目 | なぜこの項目が必要か |
|---|---|---|
| 加工要件 | 加工対象物(ワーク)の材質、最大・最小サイズ、重量 | 機械の加工範囲(ストローク)やテーブルの積載重量が、対象ワークに適しているかを判断するため。 |
| 要求される加工精度(寸法公差、面粗度、幾何公差) | 機械が持つべき基本性能を定義し、オーバースペックやスペック不足を防ぐため。 | |
| 機能・性能 | 必要な機能(ATCの工具本数、主軸回転数、早送り速度など) | 生産性目標(サイクルタイム短縮など)を達成するために不可欠な機能を明確にするため。 |
| 制御装置(CNC)のメーカーや希望する機能 | 現場の操作性やプログラムの互換性を確保し、スムーズな立ち上げを実現するため。 | |
| 設置・予算 | 設置場所の制約(スペース、床の耐荷重、搬入経路) | 物理的に設置不可能な機械を選んでしまうという、初歩的だが致命的なミスを防ぐため。 |
| 予算の上限(本体価格だけでなく、TCOを意識した総額) | 予算内で最良の選択肢を見つけるための、明確な金銭的制約を設けるため。 |
ステップ2:実機確認(テストカット)で絶対に見るべきポイントとは?
要求仕様書という名の地図とコンパスを手に、いよいよ宝の島、すなわち機械が置かれている場所へと向かいます。ステップ2は、書類や写真だけでは決してわからない機械の真の姿を、自らの五感で確かめる「実機確認」です。これは、中古工作機械の選定において最もエキサイティングであり、同時に最も集中力を要する局面。塗装の綺麗さや清掃状態に目を奪われることなく、その機械が持つ本質的な価値と、潜んでいるリスクを見抜かねばなりません。
実機確認は、単に機械を眺めるだけでは意味がありません。必ず電源を入れてもらい、要求仕様書と照らし合わせながら、その動き一つ一つを厳しくチェックします。異音はしないか、異常な振動はないか、油の漏れている箇所はないか。そして可能であれば、実機確認のクライマックスである「テストカット」の実施を強く要求すべきです。自社の製品に近い形状や材質でのテストカットを行い、その加工精度や動作の安定性を目の前で確認することこそ、その機械が本当に「使える」のかを判断するための、最も信頼できる最終試験なのです。この一手間を惜しむことが、将来の大きな後悔に繋がることを、決して忘れてはなりません。
【実践ツール】抜け漏れゼロへ!戦略的「中古工作K機械 選定基準」チェックリスト
これまで数多の理論や着眼点を学んできましたが、それらは戦場における地図や戦術書に過ぎません。ここからは、その知識を手に取り、実戦で勝利を収めるための具体的な「武器」をあなたに授けます。それが、これから提示する二つの実践的ツールです。無数の確認項目が渦巻く実機確認の現場で、思考の抜け漏れを防ぎ、冷静な判断を支える防具であり、また販売業者の本質を見抜くための鋭い矛にもなります。この実践ツールを使いこなすことこそ、これまでの学びを血肉に変え、後悔のない中古工作機械選定を完遂させるための、最後の、そして最も重要なステップとなるのです。さあ、万全の準備を整え、最終局面へと臨みましょう。
印刷して使える!物理状態から未来価値までを網羅したオリジナルチェックシート
理想と現実のギャップ。それは、中古工作機械の選定現場で誰もが直面する壁です。頭では理解していても、いざ年季の入った機械を目の前にすると、どこから手をつけて良いか途方に暮れてしまうもの。その暗闇を照らし、あなたの進むべき道を明確にする羅針盤が、このオリジナルチェックシートに他なりません。本記事で解説してきた「物理的健全性」「未来価値」「運用適合性」「TCO」という、戦略的な中古工作機械の選定基準の全てをここに凝縮しました。これを印刷して手に持ち、一つ一つの項目を指差し確認しながら冷徹に評価を下すことで、あなたは感情や印象に流されることなく、客観的なデータに基づいた最適な意思決定を下すことができるようになります。
| カテゴリ | 戦略的チェック項目 | 評価(A/B/C) | 特記事項・懸念点 |
|---|---|---|---|
| 物理的健全性 | 主軸:異音、異常発熱、ツールクランプ力、振れ精度は許容範囲内か | ||
| 摺動面・ボールねじ:摺動面の傷やカジリ、バックラッシの大きさは問題ないか | |||
| CNC・電気系統:制御盤内の汚損、配線の劣化、冷却ファンの異音はないか | |||
| 油圧・空圧・潤滑:オイル漏れ、圧力の低下、潤滑油の供給状態は正常か | |||
| 未来価値 | 拡張性(レトロフィット):主要構造部の剛性は高く、将来のCNC換装や自動化に対応できそうか | ||
| 部品供給の継続性:機械・CNCメーカーは現存するか。主要部品の入手性はどうか | |||
| 運用適合性 | 互換性:ツーリング、治具、NCプログラムは既存設備と流用可能か | (非互換の場合の追加コストを記載) | |
| 操作性・保守性:現場担当者が直感的に操作できるか。日常点検は容易か | |||
| TCO(総所有コスト) | 隠れた初期費用:基礎工事、付帯設備(コンベア等)の追加費用は発生しないか | (概算費用を記載) | |
| ランニングコスト:消費電力、消耗部品のコストは許容範囲か | (新品との比較を記載) |
この質問をすればプロとわかる!販売業者へのヒアリング項目リスト
中古工作機械の選定とは、詰まるところ人間と人間の取引です。「誰から買うか」という選定基準の重要性は、既に述べた通り。このヒアリング項目リストは、単なる質疑応答のためのものではありません。それは、販売業者の知識レベル、誠実さ、そして顧客に対する真摯な姿勢という、目に見えない価値を測るためのリトマス試験紙なのです。これらの質問に、よどみなく、かつ具体的に答えられる業者こそ、あなたの信頼に値するパートナー候補と言えるでしょう。曖昧な返答を繰り返したり、質問の意図すら理解できなかったりする相手からは、距離を置くのが賢明です。このリストを懐刀として、自信を持って交渉の場に臨んでください。
| 核心を突く質問項目 | 質問の意図・確認すべきポイント | 期待される回答 / 警戒すべき回答 |
|---|---|---|
| 「この機械の、前オーナーの業種と主な加工内容を教えていただけますか?」 | 機械にどのような負荷がかかってきたか(過酷な重切削か、軽負荷の仕上げか)を推測し、内部の疲弊度を測る。 | ◎「主にアルミの部品加工で、精度を要する仕上げに使われていました」 ×「さあ…ちょっと分からないですね」 |
| 「過去のメンテナンス履歴や、主要部品(主軸、ボールねじ等)の交換履歴はありますか?」 | 機械が大切に扱われてきたか、また高額部品の寿命が近いかを判断する。業者の情報管理能力と透明性を確認する。 | ◎「はい、こちらに整備記録があります。3年前に主軸ベアリングを交換済みです」 ×「特にないと聞いています(記録がない)」 |
| 「このCNCモデルについて、メーカーの修理サポートや部品供給は、あと何年くらい期待できますか?」 | 将来の故障リスクと、機械の事実上の寿命を見極める。業者が業界情報に精通しているかを試す。 | ◎「このモデルですと、メーカーからはあと5年は供給可能と聞いていますが、中古部品の流通も多いのでご安心を」 ×「大丈夫だと思いますよ」 |
| 「保証の範囲について、部品代だけでなく出張費や技術料も含まれるのか、具体的な書面でいただけますか?」 | 口約束ではなく、書面で保証内容を明確にさせる。トラブル時の責任範囲を確定させる。 | ◎「もちろんです。保証規定を明記した見積書と契約書をご用意します」 ×「ケースバイケースですね…」 |
中古工作機械の選定後も重要!導入後の価値を最大化する運用術
長きにわたる選定の旅路の果てに、理想の一台と巡り会い、契約書にサインした瞬間。それは、大きな安堵と共に訪れることでしょう。しかし、それは決して物語の終わりではありません。むしろ、これから始まる新たな物語の序章に過ぎないのです。中古工作機械という投資の価値を最大化し、真の利益へと昇華させられるかどうかは、まさに導入後の運用という日々の実践にかかっています。選定までの努力を無駄にせず、その価値を何倍にも高めるための運用術。これを知らずして、あなたの工場が真の競争力を手に入れることはできないのです。
安定稼働を実現する初期メンテナンスと、日常点検の習慣化
中古工作機械は、人間と同じ。長年慣れ親しんだ環境から、あなたの工場という新しい職場に移ってきたばかりの状態では、その能力を100%発揮することはできません。新しい環境に馴染ませ、本来の性能を引き出すための重要な儀式。それが、導入直後に行うべき「初期メンテナンス」です。そして、その健康状態を長期的に維持し、最高のパフォーマンスを発揮させ続ける秘訣が、「日常点検」の習慣化に他なりません。日々の小さな気遣いと記録の積み重ねが、将来発生し得たはずの莫大な修理費用と、生産停止という最悪の事態からあなたを守る、最も確実な保険となるのです。
| 点検フェーズ | 推奨される具体的なメンテナンス・点検項目 | その目的と期待される効果 |
|---|---|---|
| 導入直後 (初期メンテナンス) | ・全潤滑油、作動油、クーラント液の交換 ・各種フィルター類の清掃または交換 ・機械全体の水平出し(レベリング)の再調整 ・基本的な精度測定(バックラッシ、ピッチ誤差等) | 前オーナーの使用環境の影響をリセットし、機械を最適な初期状態に戻す。長期安定稼働の礎を築く。 |
| 日常点検 (始業前) | ・潤滑油、作動油の量と汚れの確認 ・摺動面や各部の異音、異常な振動の有無 ・油圧・空圧ユニットの圧力計の確認 ・安全カバーやインターロックの正常作動確認 | トラブルの兆候を早期に発見し、軽微なうちに対処する。日々の変化を記録することで、機械の状態を正確に把握する。 |
| 定期点検 (週次/月次) | ・制御盤の冷却ファンの清掃 ・各モーターや摺動面の清掃と給脂 ・ATC(自動工具交換装置)の動作確認 ・チップコンベア等の付帯設備の清掃 | 日常点検では見えない部分の劣化を防ぎ、機械寿命を延ばす。計画的なメンテナンスにより、突発的な故障を予防する。 |
補助金を活用した賢い設備投資:中古工作機械でも対象になる制度とは?
「中古設備は、どうせ補助金の対象外だろう」という、根強い思い込み。それは、あなたの会社の成長機会を大きく損なっている、非常にもったいない誤解かもしれません。実は、国の主要な補助金制度(例:ものづくり補助金、事業再構築補助金など)において、一定の要件を満たすことで、中古工作機械の導入も立派な補助対象となり得るのです。もちろん、新品設備に比べて要件が厳しくなる場合(例:3社以上の相見積もりの必須化など)や、申請には相応の手間と時間を要します。しかし、この制度を戦略的に活用しない手はありません。補助金という外部からの追い風を受けることは、中古工作機械の導入におけるTCO(総所有コスト)を劇的に改善し、あなたの会社の投資体力を温存しながら競争力を飛躍させる、極めて賢明な財務戦略なのです。制度の詳細は年々変化するため、必ず中小企業庁などの公的機関が発信する最新情報を確認し、この千載一遇のチャンスを逃さないようにしてください。
まとめ
長い旅路の末、ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。あなたは今、単に「安い中古機械の探し方」を知ったのではありません。価格という一点に囚われた視点から解放され、機械の過去・現在・未来を見通し、自社の成長戦略と結びつけて一台を選び抜くための、多角的で強靭な「思考のフレームワーク」を手に入れたのです。
物理的な健全性という「過去」を見抜き、レトロフィットの可能性という「未来」を測り、TCO(総所有コスト)という「生涯」を計算し、そして何より「誰から買うか」という信頼のパートナーシップを築く。もはやあなたは、カタログスペックに惑わされるだけの買い手ではなく、機械の声なき声に耳を澄まし、その一台が持つ真の価値を読み解く「目利き」と言えるでしょう。
中古工作機械の選定とは、単にコストを削減する行為ではなく、自社の未来を設計し、新たな価値を創造するための、極めて戦略的な投資活動に他ならないのです。この奥深い選定の旅路において、もし信頼できるパートナーと共に歩みたいとお考えでしたら、こちらの問い合わせフォームから、一度専門家の声を聞いてみるのも一つの賢明な選択肢かもしれません。一台の機械との出会いが、あなたの会社の、ひいては日本のものづくりの未来をどう変えていくのか。その壮大な探求の物語は、まさに今、あなたのその一歩から始まるのです。

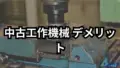
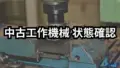
コメント