「中古工作機械、驚くほど安いけど…本当に大丈夫?」その胸騒ぎ、実はベテラン経営者だけが持つ鋭い直感の表れです。価格表に並んだゼロの数に心を奪われ、数年後に「こんなはずではなかった」と頭を抱える。それはまるで、破格のヴィンテージカーを手に入れたつもりが、エンジンは寄せ集め、フレームは事故で歪んでいた、という笑えない結末に酷似しています。初期投資を抑えるという甘い夢が、終わりの見えない修理と生産停止という悪夢に変わる瞬間を、私たちは専門家として何度も目撃してきました。
しかし、ご安心ください。この記事は単に中古工作機械が抱えるデメリットを並べ立て、あなたを怖がらせるための脅しのカタログではありません。最後までお読みいただければ、あなたは価格という表面的な魅力に惑わされることなく、機械の奥深くに潜む真の価値とリスクを見抜く「プロの目」を手に入れることができます。無数の地雷が埋められた中古市場という荒野の中から、安全かつ確実に「お宝」だけを掘り当てるための具体的な知識とチェックリスト。それこそが、あなたの会社の未来を確固たるものにする最強の武器となるでしょう。
| この記事で解決できること | この記事が提供する答え |
|---|---|
| 見た目じゃ分からない「故障リスク」、一体どうやって見抜くの? | 機械の「カルテ(整備記録)」と「健康診断(試運転)」で9割は見抜けます。その具体的なチェックポイントを徹底解説します。 |
| 「保証付き」と書いてあるけど、その言葉を本当に信用していいの? | 契約書の「免責事項」に全ての罠が隠されています。保証が機能しないケースと、あなたの権利を守るための条項を教えます。 |
| 安い本体価格の裏に隠された、本当の「総取得コスト」はいくら? | 本体価格を超えることも珍しくありません。輸送・設置・インフラ工事という「見えない費用」の全貌を明らかにします。 |
中古工作機械の導入は、単なる「買い物」ではありません。それは、過去の技術と自社の未来を天秤にかける、極めて高度な「投資判断」なのです。この記事では、中古工作機械のデメリットを一つひとつ丁寧に解剖し、それらを乗り越えて賢明な決断を下すための実践的な知恵を、出し惜しみすることなく全てお伝えします。あなたの常識をアップデートし、ライバルに静かな差をつける準備はよろしいですか?それでは、最初の地雷である「故障リスク」の正体から、共に暴いていきましょう。
中古工作機械の故障リスク:購入前に見極めるべき潜在的トラブル
中古工作機械を導入する上で、誰もが最初に懸念するデメリット。それは、やはり「故障のリスク」に他なりません。新品の機械とは異なり、これまでの稼働で蓄積された疲労や摩耗が、目に見えない形で潜んでいる可能性があります。それはまるで、長年連れ添った相棒の隠れた古傷のようなもの。しかし、そのリスクは闇雲に恐れるものではありません。中古工作機械が抱える潜在的なトラブルの発生箇所やその原因を正しく理解し、購入前に的確に見極めることさえできれば、このデメリットは十分に管理可能なものとなるのです。大切なのは、価格という魅力的な側面に目を奪われるだけでなく、その機械が歩んできた歴史と向き合い、健康状態を冷静に診断する視点を持つことです。これから解説するポイントを押さえ、賢明な選択の一助としてください。
主要故障箇所(主軸・制御装置・駆動系)とその典型的な原因
工作機械の心臓部とも言える箇所は、主に「主軸」「制御装置」「駆動系」の三つに大別されます。これらの主要箇所に一度トラブルが発生すると、生産ラインの停止はもちろん、修理には高額な費用と長い時間を要することも少なくありません。中古工作機械のデメリットを回避するためには、これらのウィークポイントを事前に把握しておくことが極めて重要です。長年の稼働は、これらの精密な部品に確実に影響を与えています。前オーナーがどのような加工を行ってきたかによっても、その疲労度は大きく変わるもの。以下の表で、それぞれの箇所で起こりうる典型的な故障とその原因を深く理解していきましょう。
| 主要故障箇所 | 典型的な故障内容 | 主な原因 | 加工への影響 |
|---|---|---|---|
| 主軸(スピンドル) | ・異音、振動の発生 ・主軸の振れ(芯ブレ) ・発熱の増大 | ・主軸ベアリングの摩耗、寿命 ・衝突(クラッシュ)による損傷 ・潤滑不良 | ・加工面の面粗度悪化 ・加工精度の低下 ・工具寿命の短縮 |
| CNC制御装置 | ・特定のアラームが頻発 ・画面表示の不具合 ・プログラムの読み込みエラー | ・電子基板の経年劣化(コンデンサ等) ・バッテリーの消耗 ・冷却ファンの故障による熱暴走 | ・機械の誤作動、暴走 ・突然の動作停止 ・加工プログラムの損失 |
| 駆動系(ボールねじ・ガイド) | ・位置決め精度の悪化 ・異音(キーキー、ゴロゴロ音) ・バックラッシの増大 | ・ボールねじ、リニアガイドの摩耗 ・サーボモーターの性能低下 ・潤滑システムの不具合 | ・寸法精度の悪化 ・円弧切削時の段差発生 ・加工面のビビリ(振動模様) |
これらの故障は単独で発生するだけでなく、相互に関連し合っているケースも少なくありません。例えば、駆動系の摩耗を補うために制御パラメータを無理に調整し、結果としてサーボモーターに過大な負荷がかかっている、といった具合です。中古工作機械を選ぶ際は、一つの症状だけでなく、機械全体を俯瞰して状態を判断する総合的な視点が求められるのです。
主軸の振れ・異音とベアリングの寿命
主軸は、工具を保持し高速で回転させる、まさに加工の要。この部分から発生する「振れ」や「異音」は、見過ごすことのできない重大な劣化サインです。主軸の先端で発生するミクロン単位の振れは、そのまま加工精度に反映され、製品の品質を著しく損ないます。その主な原因は、内部に組み込まれた主軸ベアリングの摩耗や損傷に他なりません。ベアリングは消耗品であり、長時間の高速回転や重切削による負荷、あるいは過去の衝突事故によって、その寿命は着実に削られていきます。「ゴロゴロ」「シャー」といった異音は、ベアリングが限界に近いことを示す悲鳴とも言えるでしょう。主軸のオーバーホールやベアリング交換は、数百万円単位の費用と数週間のダウンタイムを要する大修理に繋がるため、中古工作機械の選定においては最も注意深くチェックすべきデメリットの一つなのです。
CNC制御装置のエラー履歴と基板の経年劣化
機械の頭脳であるCNC制御装置もまた、中古工作機械における見逃せないデメリットを内包しています。特に注目すべきは、制御盤に記録されている「エラー履歴(アラーム履歴)」です。過去にどのようなエラーが、どのくらいの頻度で発生したかを確認することで、その機械が抱える慢性的な問題を推測できます。例えば、特定の軸に関するサーボアラームが頻発していれば、モーターやアンプ、あるいはケーブルに何らかの問題を抱えている可能性が高いと判断できるでしょう。さらに深刻なのは、外観からは判断しにくい電子基板そのものの経年劣化です。基板上のコンデンサの膨張や液漏れ、ハンダのクラックといった時限爆弾のような問題は、ある日突然、機械を沈黙させる原因となり得ます。古い制御装置は、修理用の部品が既に生産終了となっているケースも多く、故障が即、機械の寿命を意味することさえあるのです。
稼働履歴とメンテナンス記録から読み解く故障予兆
機械本体の状態を直接確認することはもちろん重要ですが、それと同じくらい価値ある情報源が「稼働履歴」と「メンテナンス記録」です。これらは、いわば機械の健康診断書やカルテに相当します。どのような環境で、どのような負荷の加工を、どれくらいの時間行ってきたのか。そして、それに対してどのような手当(メンテナンス)が施されてきたのか。これらの記録を丹念に読み解くことで、目には見えない故障の予兆を捉えることが可能です。例えば、総稼働時間が短くても、常に重切削ばかりを行っていた機械は、見た目以上に疲労が蓄積していると考えられます。逆に、定期的な摺動面オイルの交換や、メーカーによる年次点検の記録がしっかりと残っていれば、大切に扱われてきた証拠となります。中古工作機械のデメリットを語る上で、記録が不十分、あるいは存在しない機械は、その経歴が不明であるという一点において、非常に高いリスクを抱えていると判断せざるを得ません。
購入前試運転で必須のチェック項目リスト
中古工作機械の購入を決断する前に、必ず実施すべきなのが「試運転」です。カタログスペックや外観の綺麗さだけでは、その機械が持つ本当の実力や隠れたデメリットを見抜くことはできません。実際に電源を入れ、各部を動かしてみることで初めて明らかになる問題点が数多く存在します。しかし、ただ漠然と動かすだけでは不十分。目的意識を持って、チェックすべき項目を事前にリストアップしておくことが重要です。以下の表は、試運転の際に最低限確認すべき必須項目をまとめたものです。これらのポイントを一つひとつ指差し確認するくらいの気持ちで臨むことが、後悔のない選択へと繋がります。
| チェック項目 | 具体的な確認方法 | 判断基準・見るべきポイント |
|---|---|---|
| 各軸の動作と異音 | ・手動(ハンドル/JOG)で各軸を全ストローク動かす。 ・自動(G00/G01)で様々な速度で動かす。 | ・動作はスムーズか、引っ掛かりはないか。 ・「キーキー」「ゴロゴロ」といった異音はしないか。 |
| 主軸の回転と異音 | ・低速から最高回転数まで、段階的に回転数を上げていく。 | ・回転は滑らかか、異常な振動はないか。 ・ベアリングからの異音(シャー、ゴロゴロ音)はないか。 |
| ATC/タレットの動作 | ・工具交換(ATC)や刃物台の旋回(タレット)を複数回繰り返す。 | ・一連の動作に遅延や異音、引っ掛かりはないか。 ・工具の着脱はスムーズか。 |
| 油圧・空圧ユニット | ・油圧ポンプやコンプレッサーを稼働させ、圧力計を確認する。 | ・規定の圧力まで正常に上昇し、安定しているか。 ・作動油やエアの漏れはないか。 |
| テストカット(可能であれば) | ・簡単な形状(円、四角など)を実際に加工してみる。 | ・加工面の面粗度や、寸法が指示通りに出ているか。これこそが機械の総合的な健康状態を示す最も確かな指標です。 |
避けられない性能劣化:中古工作機械の精度と生産性の実態
中古工作機械が抱えるもう一つの根深いデメリット、それは「故障」という突発的なトラブルとは別に、確実に進行する「性能の劣化」です。新品時に誇ったカタログスペック上の加工精度や速度は、あくまでも未使用状態での理想値。長年の稼働という名の戦歴は、機械の隅々に摩耗や疲労を刻み込み、その性能を少しずつ、しかし確実に蝕んでいきます。これは、どれだけ丁寧なメンテナンスを施したとしても完全に避けることはできません。この性能劣化という現実は、日々の生産性や製品の品質にじわじわと影響を及ぼします。重要なのは、この避けられない性能劣化の実態を正しく理解し、自社が求める生産レベルや品質基準とその機械の現状性能との間に、許容できないギャップがないかを見極めることです。
経年劣化による加工精度の低下と許容範囲の見極め方
中古工作機械における性能劣化の影響が最も顕著に現れるのが、「加工精度」の低下です。機械の骨格を成す摺動面や、動きを司るボールねじ、リニアガイドといった部品は、何万、何十万回という往復運動の末、ミクロン単位で摩耗していきます。この摩耗が蓄積すると、機械が動く際の「遊び」であるバックラッシが増大し、指令値通りに正確な位置決めができなくなります。その結果、加工した部品の寸法がばらついたり、真円を削ったはずが僅かに楕円になったりと、品質の不安定さを招くのです。この精度の低下が、自社の製品に求められる公差の範囲内に収まっているかを見極めることが、中古機械選定の生命線となります。見極めの方法としては、ダイヤルゲージやレーザー測定器を用いたピッチ誤差測定や、実際にテストカットを行い、その寸法を三次元測定機などで精密に計測することが最も確実な手法と言えるでしょう。
応答速度の低下がサイクルタイムに与える影響
見過ごされがちですが、生産性に直接的な影響を与えるのが「応答速度の低下」というデメリットです。工作機械の動作は、CNC制御装置からの指令に対し、サーボモーターがどれだけ機敏に反応するかで決まります。しかし、モーターや駆動回路は経年によりその応答性が鈍化していくのです。これにより、例えば指令された位置でピタリと停止するまでの時間がわずかに長くなったり、早送り(G00)の加減速が新品時に比べて緩慢になったりします。一つ一つの動作における遅れはコンマ数秒の世界かもしれません。しかし、一つの製品を加工するために何百、何千という動作を繰り返す大量生産の現場において、このわずかな遅れの蓄積は、1日、1ヶ月、1年という単位で見たときに、無視できないサイクルタイムの増大、すなわち生産性の低下に直結するのです。特に、高速・高頻度で工具交換を行うマシニングセンタなどでは、この影響はより顕著に現れるでしょう。
熱変位の増大と加工安定性の関係
長時間連続で稼働させた際に、加工の安定性を脅かす要因となるのが「熱変位」です。工作機械は、主軸の回転やモーターの駆動、摺動部の摩擦など、様々な要因で熱を発生させます。新品の機械は、これらの熱を効率的に排出し、機械全体の温度を安定させるための冷却装置や設計上の工夫が施されています。しかし、中古工作機械では、この熱との戦いにおいて不利な状況が生まれます。冷却装置の能力低下や冷却液配管の詰まり、あるいは摺動面の摩耗による摩擦熱の増大などが原因で、機械が新品時よりも熱を持ちやすくなるのです。機械のフレームが熱によって膨張すると、加工基準点が微妙にズレてしまい、朝一番に加工した部品と、数時間後に加工した部品とで寸法が変わってしまうといった問題を引き起こします。この熱変位の増大は、加工の安定性を損なう厄介なデメリットであり、恒温管理されていない工場環境では特に注意が必要なポイントです。
部品供給の壁:生産終了(廃番)部品とサプライチェーンのリスク
中古工作機械の導入を検討する際、コストメリットの裏側には無視できない大きなデメリットが潜んでいます。それが、時として修理そのものを不可能にする「部品供給の壁」です。新品であれば保証のもと、必要な部品は速やかに供給されます。しかし、長い年月を経てきた中古工作機械は、その心臓部を構成する部品がすでに生産終了(廃番)となっているケースが少なくありません。それはまるで、製造された時代に取り残されたタイムカプセルのよう。一度その扉(故障)が開かれたとき、中を修復するための鍵(部品)は、もはやどこにも存在しないかもしれないのです。この部品が入手できないというリスクは、単なる修理の遅延ではなく、投資した機械が価値を失う「完全停止」という最悪のシナリオに直結する、極めて深刻なデメリットと言えるでしょう。
メーカーの部品保有期間と入手困難な特定部品
一般的に、工作機械メーカーが補修用部品を保有する期間は、その機械の製造が終了してから約10年程度とされています。この期間内であれば、多くの場合、純正部品を取り寄せて修理することが可能です。しかし、この「魔法の期間」を過ぎた途端、状況は一変します。メーカーに問い合わせても「在庫なし」「供給不可」という非情な返答が返ってくることが珍しくなくなるのです。特に、その機械のためだけに設計された専用の電子基板や、特殊な形状のギア、メーカー独自のセンサーなどは、代替品が存在しないことがほとんど。これらは、中古工作機械の安定稼働を脅かすアキレス腱に他なりません。市場に流通している中古品を探し回るか、あるいは存在しない部品を一から製作するという、時間もコストも膨大にかかる選択を迫られることになります。この部品の枯渇こそ、中古工作機械が抱える時限爆弾のようなデメリットなのです。
代替品・リビルド品・サードパーティ製部品の品質と互換性
純正部品の入手が絶望的となったとき、いくつかの代替策が選択肢として浮上します。しかし、これらの選択肢は新たなリスクを伴う諸刃の剣。品質や互換性の問題から、結果的により大きなトラブルを招く可能性も否定できません。それぞれの特徴と、潜むデメリットを正しく理解しておく必要があります。
| 部品の種類 | 概要と特徴 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|---|
| 代替品 | 現行モデルや他機種の部品を加工・改造して流用するもの。 | ・比較的、入手しやすい可能性がある。 ・最新の技術が反映されている場合がある。 | ・完全な互換性は保証されない。 ・取り付けに専門的な加工や調整が必要。 ・予期せぬ不具合を誘発するリスク。 |
| リビルド品 | 使用済みの純正部品(コア)を専門業者が分解・洗浄・修理し、再製品化したもの。 | ・純正品と同等の性能や信頼性が期待できる。 ・新品の純正品よりは安価な場合が多い。 | ・故障した部品(コア)の返却が前提となる。 ・リビルド業者の技術力に品質が左右される。 |
| サードパーティ製部品 | 純正メーカー以外の企業が製造した互換部品。 | ・価格が安価なことが多い。 ・純正品が廃番でも入手できる可能性がある。 | ・品質、精度、耐久性にばらつきが大きい。 ・「互換品」と謳っていても実際には適合しないトラブルが頻発する。 |
これらの選択肢は、緊急時には頼りになる存在です。しかし、安易にサードパーティ製の安価な部品に飛びついた結果、すぐに故障してしまったり、周辺の部品まで破損させてしまったりするケースは後を絶ちません。中古工作機械のデメリットを乗り越えるためには、こうした代替策を用いる際にも、信頼できる業者を選び、その品質を慎重に見極めるリテラシーが求められるのです。
緊急時の部品調達リードタイムと生産停止期間の想定
いざ、生産ラインの要である機械が停止したとき、そのダウンタイムは一刻一秒がコストに跳ね返ります。新品の機械であれば、メーカーの迅速な対応により数日で復旧することも可能でしょう。しかし、廃番部品を抱えた中古工作機械の場合、そのシナリオは通用しません。まず、部品を探し出すための長い旅が始まります。国内のあらゆる中古部品業者に問い合わせ、インターネットを駆使し、時には海外のネットワークまで辿る必要が出てきます。運良く見つかったとしても、そこからの輸送リードタイムは数週間、場合によっては数ヶ月を要することも。もし、代替する部品がどこにも存在しなかった場合、図面を起こして一から製作するという最終手段に至りますが、そうなれば生産が停止する期間は計り知れません。この「いつ復旧するかわからない」という不確実性こそ、中古工作機械を導入する上で覚悟すべき最大のデメリットの一つ。それは、生産計画そのものを根底から揺るがしかねない、非常に大きな経営リスクなのです。
技術サポートの断絶:メーカー保証が切れた後の保守体制
中古工作機械のデメリットは、機械という「モノ」自体の問題に留まりません。それを支える「ヒト」、すなわち技術サポート体制が失われているという点も、極めて重大な問題です。新品購入時には当たり前のように付随してくるメーカーの手厚い保証や、専門知識を持ったサービスマンによる迅速なサポート。しかし、機械が古くなるにつれて、その頼みの綱は少しずつ、そして確実に細くなっていきます。やがて、完全に断絶してしまったとき、あなたの工場はトラブルの荒波に羅針盤も海図もなしに投げ出された船と同じ。どこに連絡すればいいのか、誰が直せるのかさえ分からない「サポートの孤立」は、中古工作機械の価格的なメリットをいとも簡単に吹き飛ばしてしまうほどの破壊力を持っているのです。
年式で変わるメーカーサポートの可否とサービス内容
「メーカー製だから安心」という考えは、古い中古工作機械には必ずしも当てはまりません。メーカーにもサポートを提供できる限界があり、機械の年式、つまり製造からの経過年数によってその対応は劇的に変化します。一般的に、製造終了から10年を境にサービス内容は段階的に縮小され、やがては完全に終了するのが通例です。このサポートレベルの低下は、中古工作機械を選定する上で極めて重要な判断材料となります。
| 機械の年式(製造終了後の経過年数) | メーカーサポートのレベル | 想定される具体的な状況 |
|---|---|---|
| ~10年程度 | ◎ 充実 | 部品供給、出張修理、電話での技術相談など、新品に近い手厚いサポートが期待できる期間。 |
| 10年~15年程度 | △ 制限付き | 主要な補修部品は在庫限りとなる。その機械を熟知したベテラン技術者が退職している可能性もあり、修理を断られるケースも出始める。 |
| 15年以上 | × 期待不可 | 原則としてメーカーのサポートは完全に終了。電話で問い合わせても「弊社では対応できません」と回答される可能性が非常に高い。 |
このように、機械の戸籍とも言える年式は、その機械が将来トラブルに見舞われた際に、メーカーという最大の拠り所を頼れるかどうかを決定づける生命線なのです。特に15年以上経過した機械は、もはやメーカーの庇護下にはない「孤児」のような存在であると認識しておく必要があるでしょう。
販売店や専門修理業者が提供するサポート範囲と契約形態
メーカーのサポートが期待できなくなった古い機械にとって、頼みの綱となるのが、その機械を販売した中古販売店や、メーカーの垣根を越えて修理を請け負う民間の専門修理業者です。彼らは、長年の経験で培ったノウハウや独自の部品調達ネットワークを駆使し、メーカーが見放した機械の延命に力を貸してくれます。サポートの形態としては、年間の保守契約を結んで定期的なメンテナンスを行うものから、故障発生時に都度対応するスポット修理まで様々です。しかし、ここで注意すべきデメリットは、業者によって技術力や対応範囲に大きなばらつきがあるという点。電気系に強い業者、メカ系に強い業者など得意分野が異なるため、自社の機械の特性と業者の専門性を見極める必要があります。また、契約内容を詳細に確認しないと、「基本料金は安いが、出張費や部品代で結局高額になった」という事態も起こり得ます。信頼できるパートナーを見つけられるかどうかが、中古工作機械を安心して使い続けるための鍵となるでしょう。
技術資料(回路図・パーツリスト)の入手可否と重要性
どんなに腕の良い医者でも、カルテやレントゲン写真がなければ正確な診断は下せません。工作機械の修理においても全く同じことが言えます。その機械の「カルテ」にあたるのが、「回路図」「ラダー図」「パーツリスト」「メンテナンスマニュアル」といった一連の技術資料です。これらの資料がなければ、トラブルが発生した際に、どの部品が故障しているのか、その部品の型番は何なのかを特定することが極めて困難になります。特に複雑な電気系統のトラブルでは、回路図がなければ原因究明は不可能と言っても過言ではありません。中古工作機械を購入する際には、これらの技術資料がすべて揃っているかを確認することが絶対条件です。もし、これらの資料が一つでも欠けているのであれば、それはその機械が抱える非常に大きなデメリットです。なぜなら、それは万が一の際に、修理という治療を施すための最も重要な手がかりを失っていることに他ならないからです。
契約書の罠「隠れた瑕疵」:外観から判断できない内部の問題点
中古工作機械の取引において、外観の美しさや清掃の行き届いた状態は、必ずしもその機械の健康状態を保証するものではありません。塗装の下に隠された亀裂、静かに時を刻む時限爆弾のような内部の欠陥。これこそが、法律用語でいう「隠れた瑕疵」、現在の民法では「契約不適合」と呼ばれる、中古工作機械が抱える極めて厄介なデメリットです。この問題の根深さは、購入時点では買い手が通常の注意を払っても発見できず、導入後に初めて発覚するという点にあります。その時、契約書の一文が、あなたの権利を守る盾にも、あるいは全てを諦めさせる鎖にもなり得るのです。「現状有姿渡し」という言葉の裏に潜む、売り手の責任放棄という意図を見抜く洞察力が、中古工作機械の買い手には不可欠と言えるでしょう。
法的に問われる「隠れた瑕疵」の定義と具体的事例
「隠れた瑕疵」、すなわち「契約不適合」とは、売買契約の対象となった機械が、種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しない状態を指します。中古工作機械の文脈で言えば、カタログスペック通りの性能が出なかったり、安全上問題のある状態だったりすることがこれに該当します。重要なのは、この不適合が「購入時に通常の注意を払っても発見できなかった」という点であり、これが後々のトラブルの火種となるのです。売り手は、この契約不適合に対して、追完請求(修理や代替品の納品)、代金減額請求、損害賠償請求、そして契約解除といった責任を負うことが法律で定められています。しかし、この責任が契約によって免除されているケースも少なくありません。以下に、契約不適合に該当しうる典型的な事例を示します。
| 不適合の種類 | 具体的な事例 | 買い手が被る損害 |
|---|---|---|
| 品質に関する不適合 | ・ベッドやコラムの鋳物内部に、目視不可能なクラックが存在した。 ・主軸ベアリングが許容範囲を超えて摩耗しており、指定の回転数で異音が発生する。 | ・加工精度の著しい悪化。 ・機械の突然の破損、重大事故のリスク。 |
| 性能に関する不適合 | ・テストカットでは問題なかったが、長時間の連続運転で熱変位が多発し、寸法が安定しない。 ・ заявявленная早送り速度が出ず、サイクルタイムが想定より長くなる。 | ・生産計画の未達、生産性の低下。 ・不良品の多発によるコスト増大。 |
| 安全性に関する不適合 | ・本来あるべき安全カバーやインターロックが、作業性向上のため無断で取り外されていた。 ・電気系統に不正な改造が施されており、漏電の危険性があった。 | ・労働災害の発生リスク。 ・工場の安全基準を満たせず、稼働許可が下りない。 |
購入後に発覚しやすい内部クラック、不正な改造、精度不良
中古工作機械のデメリットの中でも、特に買い手を悩ませるのが、購入後の稼働テストや、生産ラインに組み込んで初めて明らかになる深刻な問題です。例えば、鋳物内部に存在する微細な「内部クラック」。これは過去の衝突事故や長年の金属疲労によって生じますが、超音波探傷などの専門的な非破壊検査を行わない限り、その存在を知ることはできません。また、前オーナーが生産効率を優先するあまり、メーカーが設定した安全装置を無効化したり、制御パラメータを危険な領域に変更したりする「不正な改造」も後を絶ちません。これらは一見すると正常に動作するため、非常に見抜きにくいのです。さらに、短時間の試運転ではごまかせても、特定の条件下でのみ顕在化する「精度不良」も深刻な問題です。これらは熟練の目をもってしても外部からの目視や短時間の試運転だけでは見抜くことが極めて困難であり、中古工作機械のデメリットの中でも特に悪質な罠と言えるでしょう。
売買契約書で確認すべき「契約不適合責任」に関する条項
こうした目に見えないリスクから身を守るための最後の砦、それが売買契約書です。口約束がいかに甘い言葉で交わされようとも、法的な効力を持つのは紙面に記された文字だけ。特に「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」に関する条項は、一字一句を疎かにしてはなりません。安易な契約は、将来の権利を自ら放棄するに等しい行為です。中古工作機械の購入という大きな決断を下す前に、最低限、以下の項目が契約書でどのように扱われているかを、弁護士に相談することも含めて慎重に確認すべきです。口頭での「大丈夫です」という言葉は何の保証にもならず、最終的には契約書に書かれた文言がすべてを決定づけるという冷徹な事実を忘れてはなりません。
| 確認すべき条項 | その意味と注意点 |
|---|---|
| 「現状有姿渡し」の文言 | 「見たままの状態で引き渡す」という意味。この一文をもって、売り手は「契約不適合責任を一切負わない(免責)」と主張してくることが非常に多い。最も注意すべき危険な条項です。 |
| 契約不適合責任の期間 | 買い手が不適合を知ってから1年以内に通知が必要ですが、契約で「引渡し後3ヶ月」などと短縮されている場合があります。期間が不当に短くないかを確認する必要があります。 |
| 責任の範囲と内容 | 修理、代替品の提供、代金減額、契約解除など、どのような救済措置が受けられるのかが明記されているか。修理費用の負担割合(部品代、出張費など)も確認が必要です。 |
| 免責事項の有無 | 「消耗品の劣化は責任を負わない」など、責任を免れる項目が具体的に列挙されている場合があります。その範囲が妥当であるか、慎重に判断しなくてはなりません。 |
想定外の寿命短縮:中古工作機械の本当の耐用年数とは
中古工作機械を導入する際、多くの人が本体価格という初期投資の低さに目を向けます。しかし、その機械が利益を生み出す源泉である「寿命」については、意外なほど見過ごされがちです。税法上の「法定耐用年数」という言葉に安心してしまうのは、大きな落とし穴。これはあくまで減価償却のための計算上の数字であり、機械が物理的、電気的に稼働し続けられる実質の寿命とは全くの別物です。前オーナーの過酷な使用環境によって、見た目以上に寿命が削られている可能性は、中古工作機械が常に抱えるデメリットです。中古工作機械の価格という「入り口」の魅力だけでなく、その機械がいつまで価値を生み出し続けられるかという「出口」までを見通す視点こそが、賢明な投資の鍵を握るのです。
法定耐用年数と、実際の機械的・電気的寿命の乖離
多くの経営者や経理担当者は、「法定耐用年数」を機械の寿命と混同しがちですが、この二つは全く異なります。この認識のズレこそが、中古工作機械選びにおける失敗の元凶となり得ます。法定耐用年数は、あくまで税務会計上の資産価値を計画的に減少させていくための便宜的な期間に過ぎません。一方で、機械の「本当の寿命」は、物理的な摩耗が進む「機械的寿命」と、電子部品が限界を迎える「電気的寿命」という、二つの側面から考える必要があります。税務上の償却が終わった機械が、必ずしも物理的な寿命を迎えたわけではないのと同様に、まだ償却期間が残っているからといって、その機械の健康が保証されるわけでは全くないのです。
| 比較項目 | 法定耐用年数 | 実際の寿命(機械的・電気的) |
|---|---|---|
| 定義 | 税法で定められた、減価償却計算に用いる年数。(例:金属加工用のNC工作機械は10年) | 機械が物理的・電気的に、要求される性能を維持して稼働できる実質の期間。 |
| 決定要因 | 法律によって一律に定められている。 | 前オーナーの使用状況、メンテナンス頻度、稼働環境、製造品質など、無数の要因で変動する。 |
| 意味合い | 会計上の資産価値。 | 機械が生み出すことができる、将来のキャッシュフローそのもの。 |
| 中古選定時の注意点 | 参考程度にはなるが、これを基に購入を判断するのは非常に危険。 | こちらをこそ重視すべき。メンテナンス記録や試運転を通じて、残存寿命を推測する必要がある。 |
前オーナーの使用環境が機械寿命に与える影響
同じ製造年、同じ型式の機械であっても、中古市場での価値や残存寿命が大きく異なるのはなぜか。その答えは、前オーナーがどのような環境で、どのように機械を扱ってきたかに集約されます。それは人間と同じで、過酷な労働環境で休みなく働いてきたのか、それとも適度な仕事量で定期的に健康診断を受けてきたのかによって、健康寿命が大きく変わるのと全く同じ理屈です。この個体差の大きさは、予測が難しい中古工作機械のデメリットそのもの。機械の銘板に刻まれた製造年よりも、その機械が歩んできた「職歴」とも言える履歴こそが、本当の寿命を雄弁に物語っているのです。購入を検討する際は、機械そのものだけでなく、その機械が生きてきた背景を想像し、読み解く必要があります。
オーバーホールで寿命はどれだけ延びるのか?コストと効果
疲弊し、寿命が近づいた中古工作機械を蘇らせるための選択肢として「オーバーホール(O/H)」があります。これは機械を構成部品のレベルまで完全に分解し、洗浄、測定、摩耗・劣化した部品の交換や修復を行い、再度精密に組み立てて新品同様の性能を回復させる、いわば究極の再生手術です。適切に行われたオーバーホールは、確かに機械の寿命を劇的に延ばし、最新機種に匹敵する精度を取り戻すことさえ可能です。しかし、この再生には非常に高額なコストという大きなデメリットが伴います。オーバーホールは機械を蘇らせる魔法ではなく、その効果と引き換えに莫大なコストを要求する最終手段であり、その費用対効果を冷静に天秤にかける必要があります。中古本体の購入価格に数百万円から、時には一千万円を超えるオーバーホール費用が上乗せされるとなれば、果たしてそれが最適な投資だったのか、という根本的な問いに直面することになるでしょう。
本体価格以外の落とし穴:高額になりがちな輸送・設置費用
中古工作機械の魅力は、何と言ってもその初期投資の低さにあります。しかし、その価格表の数字だけを見て安易に判断を下すのは早計というもの。まるで格安の土地を見つけて喜んでいたら、そこへたどり着くための道がなく、橋を架けるのに莫大な費用がかかるような話です。中古工作機械の取引には、本体価格という氷山の一角の下に、輸送、搬入、据付、そしてインフラ整備といった、巨大で高額な付帯費用が隠されています。本体価格の安さという甘い蜜の裏には、この付帯費用という苦い毒が隠されており、総取得コストを計算した際に「こんなはずではなかった」と頭を抱えることは、中古工作機械のデメリットとしてあまりにも頻繁に起こる事態なのです。
見積もりに潜む付帯費用の内訳(解体・輸送・据付・芯出し)
「輸送・設置費用一式」という見積もりの一行に、一体どれだけの内容が詰め込まれているか、あなたは想像できるでしょうか。この一言の裏には、専門的な知識と特殊な機材を要する数々の工程が存在し、それぞれに決して安くはないコストが発生します。これらの工程を理解せずに契約を進めることは、白紙の小切手にサインをするようなもの。中古工作機械のデメリットを回避するためには、この「一式」という言葉の内訳を、自身の目で詳細に確認する必要があります。具体的にどのような費用が潜んでいるのか、その一例を見ていきましょう。
| 費用項目 | 作業内容 | 費用が高騰する主な要因 |
|---|---|---|
| 解体・搬出 | 機械を輸送可能なサイズまで分解し、元の設置場所から搬出する作業。 | ・機械が大型・複雑で分解に手間がかかる。 ・搬出経路が狭く、壁の解体などが必要になる。 |
| 輸送 | 大型トラックやトレーラーで、売り手の工場から自社工場まで機械を運ぶ。 | ・長距離輸送になる場合。 ・機械の重量やサイズが特殊で、専用車両が必要な場合。 |
| 搬入・据付 | 自社工場内へ機械を運び込み、指定の場所へ設置(アンカー固定など)する。 | ・クレーンの手配が必要になる。 ・工場入り口や通路が狭く、搬入に特殊な機材(チルタンク等)が必要。 |
| レベル・芯出し | 機械を水平に設置し、各軸の精度をミクロン単位で調整する、最も重要な仕上げ作業。 | ・高い精度が要求される機械の場合。 ・作業に時間がかかり、技術者の拘束時間が長くなる。 |
これらの付帯費用は、時として中古工作機械の本体価格に匹敵、あるいはそれを上回るケースさえあり、総取得コストを大幅に押し上げる隠れたデメリットなのです。
設置場所の耐荷重と基礎工事の要否判断
無事に機械が工場に到着したとしても、安心はできません。次なる関門は、その機械を設置する「床」そのものの問題です。マシニングセンタや大型旋盤は、数トンから、時には数十トンにも及ぶ巨大な鉄の塊。その重量に、あなたの工場の床は耐えられるでしょうか。この「耐荷重」の確認を怠ることは、中古工作機械の導入計画における致命的な見落としとなり得ます。機械の仕様書に記載された重量と、自社工場の床の設計強度を照らし合わせる作業は、絶対に省略してはならないのです。もし既存の床が機械の重量に耐えられないと判明した場合、大規模な基礎工事が必要となり、想定外の数百万円単位の出費と数週間の工期延長という、致命的な計画の狂いを生じさせます。本体を安く手に入れても、その土台作りに予算の大半を食われてしまっては、本末転倒と言わざるを得ません。
電源容量、エア供給、冷却装置などユーティリティ工事の確認点
機械という「体」を動かすには、電気、空気、油といった「血液」が必要です。中古工作機械を導入する際には、このユーティリティ(付帯設備)の供給体制が整っているかという点も、見落とされがちなデメリットの一つです。例えば、その機械が必要とする電圧や電流を、現在の工場の電源契約で賄えるでしょうか。専用の変圧器(トランス)や、太い幹線ケーブルの敷設工事が必要になるかもしれません。また、機械の動作に必要な圧縮エアの供給量は足りているか、配管工事は必要ないか。切削油を冷却するためのクーラントチラーや、工場環境を保つためのオイルミストコレクターは、そもそも今回の売買契約に含まれているのか。機械本体が格安で手に入ったとしても、それを動かすためのインフラが整っていなければ、それはただの巨大な鉄の塊に過ぎず、ユーティリティ工事という追加投資が必ず発生します。
保証期間の真実:「保証付き」でも安心できない理由
中古という不安な買い物において、「保証付き」という三文字は、まるで暗闇に差し込む一筋の光のように、買い手に安心感を与えます。しかし、その光が本物であるか、あるいは蜃気楼であるかを見極めなければなりません。新品の機械に付帯する手厚い保証と同じ感覚でいると、その期待は脆くも崩れ去るでしょう。中古工作機械の世界における保証は、多くの場合、買い手が思い描くような万能の盾ではありません。それは無数の免責事項という穴が開けられた、極めて限定的な傘のようなものなのです。「保証付き」という甘い響きに安心してはいけません。中古工作機械における保証は、多くの場合、買い手の期待を裏切る免責事項に満ちた、極めて限定的なものであるという厳しい現実があります。
中古機械における一般的な保証期間と「現状有姿渡し」のリスク
まず理解しておくべきは、中古工作機械における保証期間の短さです。手厚い業者であっても納品後3ヶ月、一般的には1ヶ月程度が関の山。中には「1週間の動作保証」といった、ないに等しい期間設定も存在します。そして、それ以上に警戒すべき契約形態が「現状有姿(げんじょうゆうし)渡し」です。これは、中古工作機械の取引で最も注意すべきデメリットを内包した言葉と言えるでしょう。
- 保証付きの場合:契約で定められた期間内・範囲内において、発生した故障の修理を売り手が保証する。ただし、その範囲は極めて限定的であることが多い。
- 現状有姿渡しの場合:「今ある、見たままの状態で引き渡します」という意味。これは事実上、売り手が引き渡し後の機械の一切の不具合について責任を負わないという意思表示。購入後にいかなる故障が発覚しようとも、買い手は売り手に責任を追及することができなくなる。
特に「現状有姿渡し」という契約は、事実上、買い手がすべての故障リスクを一方的に引き受けることを意味し、中古工作機械のデメリットが最大限に顕在化する取引形態と言えます。
保証対象となる部品・ならない部品の明確な線引き
たとえ「保証付き」の契約であっても、その中身を詳細に確認しない限り、本当の安心は得られません。なぜなら、保証には必ず「対象となる部品」と「対象とならない部品」の明確な線引きが存在するからです。買い手としては、高額で壊れやすい部品こそ保証してほしいと願うもの。しかし、売り手の論理は逆です。壊れやすく、高額な部品ほど、保証の対象外とされる傾向が強いのです。このギャップが、中古工作機械の保証という制度を複雑で分かりにくいものにしています。
| 分類 | 保証の対象になりやすい部品 | 保証の対象外になりやすい部品 |
|---|---|---|
| 機械本体 | ・主要な構造体(ベッド、コラムなど) ・主軸本体、ボールねじなど(ただし条件付き) | ・全ての消耗品(ベアリング、パッキン、オイルシール、フィルター、ワイパー等) ・摺動面カバー、窓、塗装など |
| 電気・制御系 | (ほとんどの場合、保証対象外) | ・CNC制御装置の基板全般 ・サーボモーター、サーボアンプ ・操作パネル、モニター、各種スイッチ類 |
| その他 | (ほとんどの場合、保証対象外) | ・油圧ユニット、空圧機器 ・潤滑・冷却ポンプ ・ATC(自動工具交換装置)関連部品 |
保証契約書を精査すると、最も高額で故障しやすい電気・電子部品が巧妙に保証対象から除外されているケースが多く、実質的な保証価値が極めて低いという事実に直面します。
保証修理における出張費・技術料の負担区分
保証の落とし穴は、対象部品の範囲だけではありません。最後の砦として立ちはだかるのが、「修理に伴う費用の負担区分」という問題です。仮に、運良く故障した部品が保証対象となり、新品の部品が無償で提供されることになったとしましょう。しかし、その部品を交換するために必要な、専門技術者の「出張費」や「技術料(作業工賃)」は誰が負担するのか。この点が契約書で明確にされていない場合、新たなトラブルの火種となります。驚くべきことに、中古工作機械の保証では、「部品代は売り手負担、出張費・技術料は買い手負担」というケースが少なくないのです。たとえ保証で部品代が無償になったとしても、高額な出張費や技術料を請求され、結果的に有償修理と変わらないほどの出費を強いられるという、保証の空洞化とも言える事態が起こり得るのです。
最新技術とのギャップ:現行機に劣る機能と生産性
中古工作機械を選ぶとき、私たちは価格という過去の価値に目を奪われがちです。しかし、その選択は同時に、未来の時間を犠牲にしている可能性をはらんでいます。最新の工作機械が日進月歩で遂げている技術革新。その恩恵を受けられないという事実は、単なる機能の有無という話に留まりません。それは、加工速度、精度、そして工場全体の生産性という、企業の競争力そのものに直結する、静かで、しかし決定的なデメリットなのです。まるで往年の名選手を現代のトップリーグにいきなり投入するようなもの。その経験値は尊いものの、スピードとルールの変化についていけず、本来の力を発揮できないという厳しい現実に直面するのです。
加工速度・精度を左右する制御技術(CNC)の世代間格差
中古工作機械の性能を決定づける心臓部、CNC制御装置。その進化は、スマートフォンの世代交代にも似ています。古い世代のCNCは、現代の目から見れば処理能力が著しく劣ります。プログラムの先読みブロック数が少なければ、高速で複雑な輪郭を加工する際に動きがカクカクしてしまい、滑らかな加工面は得られません。また、CPUの処理速度が遅ければ、緻密な制御が追いつかず、サイクルタイムの短縮にも限界が見えてきます。これは単に早送り速度が遅いという問題ではありません。最新のCAMシステムが生成する高精度な加工パスを、機械が忠実に再現できるか否かという、製品品質の根幹に関わる世代間の格差なのです。この見えない性能差は、特に金型加工のような高品位な曲面が求められる現場において、埋めがたい品質と時間のデメリットとなって現れるでしょう。
IoTや工場ネットワークへの接続性・拡張性の限界
現代の「賢い工場(スマートファクトリー)」は、すべての機械がネットワークで繋がり、データを共有し、生産性を最適化することが前提となっています。稼働状況の遠隔監視、予防保全のためのデータ収集、生産管理システムとの連携。これらはもはや特別なことではありません。しかし、古い中古工作機械の多くは、このデジタルの輪に加わることが極めて困難です。そもそもLANポートが存在しない、あるいは通信プロトコルが古すぎて現代のシステムと会話ができない。それは、いわば工場内での「デジタル鎖国」状態。後付けの装置で無理やり繋ごうとしても、取得できる情報が限られていたり、システムが不安定になったりと、多大なコストと労力をかけても満足な結果は得られないことが多いのです。一台の機械の接続性の限界が、工場全体のスマート化の足を引っ張るというデメリットは、想像以上に大きな損失と言えるでしょう。
省エネルギー性能と安全基準(安全カバー、インターロック等)の新旧比較
目先の本体価格だけでなく、長期的な視点で見ると、省エネルギー性能と安全基準の差も中古工作機械の大きなデメリットとなります。技術革新は、生産性だけでなく、ランニングコストや働く人の安全にも大きく貢献しているのです。新旧の機械では、これらの点において具体的にどのような違いがあるのか、以下の表で比較してみましょう。
| 比較項目 | 最新の工作機械 | 古い中古工作機械 |
|---|---|---|
| 省エネルギー性能 | ・インバータ制御による消費電力の最適化 ・待機電力削減モード(スリープ機能) ・LED照明の標準装備 | ・モーターは常時フルパワーで稼働 ・待機中の電力消費が大きい ・照明は消費電力の大きい蛍光灯や白熱灯 |
| ランニングコストへの影響 | 日々の電気代を大幅に削減し、長期的なコストメリットが大きい。 | 見えないコストとして電気代が嵩み、企業の収益を圧迫する要因となる。 |
| 安全基準 | ・国際安全規格(ISO等)に準拠 ・開扉時に機械が完全停止するインターロック ・衝突検知、回避機能など高度な安全装置 | ・当時の国内基準のみに対応 ・安全カバーやインターロックが不十分、あるいは改造により無効化されているリスクがある。 |
| 労働安全への影響 | オペレーターの安全を最優先に設計されており、労働災害のリスクが低い。 | ヒューマンエラーが重大事故に直結しやすく、現代の安全コンプライアンスを満たせない可能性がある。 |
スムーズな稼働を阻む導入後の課題と対策
中古工作機械の導入は、機械を工場に設置し、電源を入れた瞬間に完了するのではありません。むしろ、そこからが本当の始まりです。機械というハードウェアを迎え入れた後に待ち受けているのは、それを扱う「人」や、連携する「システム」といった、ソフトウェア面での数々の課題。これらは、購入前の検討段階では見過ごされがちな、しかし確実に生産の足を引っ張るデメリットとなります。どんなに優れた性能を持つ機械であっても、それを使いこなす体制が整っていなければ、宝の持ち腐れとなってしまうのです。導入後に発生しうる人的・システム的な障壁をあらかじめ想定し、対策を講じておくことが、中古工作機械を真の戦力とするためには不可欠です。
旧式操作パネルへのオペレーター習熟と教育コスト
最新の工作機械が、タッチパネルとグラフィカルなユーザーインターフェースで直感的な操作を実現しているのに対し、古い機械の操作パネルは、専門的な知識を持つ者でなければ解読困難な、無数のボタンと小さなモノクロ画面で構成されています。スマートフォンに慣れ親しんだ若い世代のオペレーターにとって、この旧式の操作方法は大きなストレスとなり、習熟までに長い時間を要します。これは単に「慣れ」の問題ではなく、貴重な人材の教育に多大な時間とコストがかかるという、明確な経営上のデメリットです。操作ミスによる機械の破損や不良品の発生リスクも高まり、結果として、一人前のオペレーターが育つまでの機会損失は計り知れないものになるでしょう。
既存CAD/CAMシステムとのデータ互換性の問題
現代のものづくりは、設計部門のCADで作られた3Dデータを、CAMシステムを介してNCプログラムに変換し、工作機械に送るというデジタルな流れが主流です。しかし、このスムーズな連携に「待った」をかけるのが、古い中古工作機械のデータ互換性の問題です。最新のCAMが生成する、滑らかで複雑な加工を実現するための長大なNCプログラムを、古いCNCのメモリ容量では受け止めきれない。あるいは、最新の加工指令コードを理解できず、エラーで停止してしまう。データ転送方法も、USBメモリやLAN接続が当たり前の現代において、いまだにフロッピーディスクやRS-232Cといった骨董品レベルのインターフェースしか備えていないケースも珍しくありません。このデータの断絶は、設計から製造までのリードタイムを著しく悪化させ、生産性向上を阻む大きな壁となるのです。
予期せぬトラブルによる生産計画への影響と代替生産の準備
これまで述べてきた故障リスク、性能劣化、部品供給の壁といった数々のデメリットは、最終的に「生産計画の破綻」という形で企業に深刻なダメージを与えます。中古工作機械を生産ラインの主軸に据えるということは、この「いつ止まるか分からない」という不確実性と常に隣り合わせであることを意味します。一つの機械の停止が、サプライチェーン全体の遅延を引き起こし、顧客からの信頼を失うことにも繋がりかねません。このリスクをヘッジするためには、中古工作機械を導入する時点で、万が一の事態を想定したバックアッププランを構築しておくことが絶対条件となります。具体的には、以下のような対策を事前に講じておくべきでしょう。
- 社内での代替生産体制の確保: 故障した際に、同じ加工ができる他の機械を遊ばせておく、あるいはすぐに段取り替えができるような体制を整えておく。
- 信頼できる外注先の確保: 緊急時に加工を依頼できる、協力工場との連携を密にしておく。品質や納期について事前に取り決めを行っておくことが重要。
- 重要部品の予備在庫: 故障が予測される高リスクな部品(基板、モーター等)について、中古品市場などで予備を確保し、自社で在庫しておく。
- 簡易的な修理技術の習得: 簡単なメンテナンスや部品交換であれば、自社の保全担当者が対応できるよう、技術研修などを行っておく。
まとめ
これまで、中古工作機械が抱える数々のデメリットを、様々な角度から紐解いてきました。故障リスク、性能劣化、部品供給の壁、サポートの断絶、契約の罠、そして最新技術とのギャップ。これらは、価格という魅力的なヴェールの下に隠された、避けては通れない現実です。機械が刻んできた時間の重みは、時に性能の低下や予期せぬ故障という形で現れ、その心臓部を修復するための部品や技術サポートが、時の流れと共に失われている可能性も否定できません。
これらのデメリットを乗り越え、中古工作機械という選択を成功に導くために本当に必要なのは、単なる価格やスペックの比較ではなく、その機械が歩んできた歴史を読み解き、隠れたリスクを見抜く深い洞察力、いわば「機械の魂」と対話するような姿勢に他なりません。一台の機械が持つ本当の価値を見極め、その未来に責任を持つことは、決して容易な道ではないのです。
もし、あなたがその複雑で奥深い世界に信頼できる案内人を求めているのであれば、まずはその道の専門家に相談してみるのも一つの賢明な選択でしょう。中古工作機械を選ぶという行為は、単なる設備投資に留まらず、過去の技術と未来の生産性を結びつける、ものづくりの歴史への新たな関わり方を探求する旅の始まりなのかもしれません。

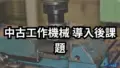
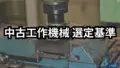
コメント