「またか…」という鈍い音と共に、高価な超硬エンドミルが無残な姿に。けたたましく鳴り響く機械のアラームが、あなたの焦燥感をさらに煽る。フライス盤の前で、焼入れされた鋼材を前に立ち尽くすあなた。その脳裏をよぎるのは、「やっぱり硬い材料は難しい」「工具寿命が短いのは仕方ない」という、半ば諦めに似た溜息ではないでしょうか。まるで気難しく、予測不能な巨匠を相手にするような熱処理材との戦い。しかし、もしその原因が、あなたの「力不足」ではなく、相手の「ご機見」を読み間違えているだけだとしたら?
フライス加工の材料適合選定について網羅的にまとめた記事はこちら
ご安心ください。この記事は、あなたの経験則という名のコンパスに、「材料科学」という名の超高精度GPSを追加するためのものです。最後まで読めば、あなたは単なるオペレーターから「熱処理材の心を読み解くマエストロ」へと進化を遂げるでしょう。突発的な工具破損の恐怖から解放され、安定した加工による劇的なコストダウンと品質向上を実現する方法が、ここにはあります。もう「硬いから」という一言で、全てを片付ける必要はありません。熱処理材が内に秘めた声に耳を澄まし、彼らとの完璧な対話を始める準備をしましょう。
この記事を読み解くことで、あなたの長年の疑問は確信へと変わります。具体的には、以下の課題に対する明確な答えが手に入ります。
| この記事で解決できること | この記事が提供する答え |
|---|---|
| なぜ熱処理材は、硬さ以上に「厄介」でトラブルが絶えないのか? | その正体は「硬さ」の裏に潜む3つの真犯人(内部構造の不均一性、熱伝導率の低下、内部応力)にあります。 |
| 「高硬度用」のはずの工具が、なぜいとも簡単に欠けてしまうのか? | 工具の「壊れ方(チッピングか摩耗か)」から逆算していないからです。原因に応じた材質・形状の選定法を解説します。 |
| 切削条件をいくら調整しても安定しないのは、一体なぜなのか? | それは「熱と力のマネジメント」という視点が欠けているから。熱は切りくずで排出し、力は加工パスで分散させる新常識を伝授します。 |
もちろん、これはほんの入り口に過ぎません。本文では、材質別の具体的な攻略法から、見落としがちな機械剛性や前後工程との連携まで、あなたの知識を体系的にアップデートします。さあ、あなたのフライス盤が奏でる音を、断末魔の悲鳴から美しいシンフォニーへと変える旅に出かけましょう。ページをスクロールしたその先には、あなたの常識を心地よく覆す発見が待っています。
- 「また工具が欠けた…」フライス加工で熱処理材を考慮すべき本当の理由
- 表面的な硬度だけで判断は危険!熱処理材の内部構造を考慮する重要性
- あなたの常識を覆す!フライス加工における熱処理材の意外な挙動
- 工具選定の失敗は9割がコレ!「破壊モード」から逆算する熱処理材への考慮
- 切削条件の最適化は「熱と力のマネジメント」- 熱処理材加工で考慮すべき新常識
- 【実践編】S45C-HからSKD11まで!材質別フライス加工で考慮すべきポイント
- トラブル発生!その時どうする?原因から対策を導く熱処理材の考慮事項
- そのセッティングで大丈夫?機械剛性と保持具が熱処理材加工に与える影響の考慮
- 加工現場のヒーローになる!前後工程まで考慮した熱処理材の段取り術
- コストダウンと品質向上を両立する、戦略的な熱処理材加工への考慮
- まとめ
「また工具が欠けた…」フライス加工で熱処理材を考慮すべき本当の理由
「また工具が欠けてしまった…」「なぜか、このワークだけ工具の寿命が極端に短い…」。フライス加工の現場で、このような悩みの声を聞くことは決して珍しくありません。特に、焼入れや調質が施された熱処理材の加工は、多くの技術者を悩ませる難敵ではないでしょうか。その原因を「ワークが硬いから」という一言で片付けてしまうのは、あまりにも早計です。実は、その背後にはもっと複雑で根深い理由が隠されています。熱処理材の加工におけるトラブルを根本から解決するためには、表面的な硬さだけではない、材料そのものが持つ本質的な特性を深く考慮する必要があるのです。
なぜ熱処理材の加工はトラブルが絶えないのか?現場の悩みあるある
熱処理材を前にした時、加工現場では実に様々な問題が発生します。工具寿命が安定せず、コスト計算が成り立たない。突然の工具破損によって機械を長時間停止させてしまい、生産計画に大きな影響が出てしまう。あるいは、どれだけ切削条件を調整しても、満足のいく仕上げ面が得られずに頭を抱える。寸法精度が安定せず、後工程である研削の取り代が変動してしまう、といった悩みも尽きません。これらの問題は、それぞれ独立しているように見えて、実はすべて根っこで繋がっています。多くの現場で繰り返されるこれらのトラブルは、熱処理材の特性に対する深い理解と、それに基づいた適切な「考慮」が欠けているというサインなのです。
「硬いから」だけじゃない!あなたが考慮すべき3つの隠れた要因
熱処理材の加工が難しい理由を、単に「HRCが高いから」という硬度だけの問題で捉えていては、本質的な解決には至りません。あなたが本当に考慮すべきは、硬さの裏に潜む、目には見えない3つの要因です。これらの要因が複雑に絡み合い、工具に対して予測不能なダメージを与えています。その結果として、工具の突発的な欠損や異常摩耗といったトラブルを引き起こしているのです。ここでは、あなたがこれから常に意識すべき、3つの隠れた要因について解説します。
| 考慮すべき要因 | 概要 | 加工への影響 |
|---|---|---|
| 1. 内部構造の不均一性 | 熱処理の冷却過程などにより、ワーク内部の金属組織や硬さが均一になっていない状態。特に厚肉部と薄肉部で差が生じやすい。 | 工具が硬い部分と柔らかい部分を断続的に切削することになり、刃先に衝撃的な負荷がかかる。これがチッピング(微小欠損)の直接的な原因となる。 |
| 2. 熱伝導率の変化 | 熱処理によって金属組織が変化し、生材(なまざい)の状態と比較して熱伝導率が著しく低下する。熱が逃げにくくなる。 | 切削時に発生した熱が工具の刃先に集中し、刃先温度が異常に上昇する。これにより、工具コーティングの劣化や刃先の軟化が進み、摩耗が急激に進行する。 |
| 3. 大きな内部応力 | 焼入れなどの急激な冷却によって、ワーク内部に大きな引張応力や圧縮応力が残留している状態。 | 加工によって材料が除去されると、内部の応力バランスが崩れて解放され、ワークに予期せぬ歪みや変形が生じる。これが寸法精度の悪化を招く。 |
この記事が提供する、経験則を超えた熱処理材加工の新たな視点
これまで多くの現場では、熱処理材の加工は「職人の勘」や「過去の経験則」に頼らざるを得ない領域でした。「この材質なら、これくらいの切削速度で…」といった暗黙知は、もちろん貴重な財産です。しかし、それだけではトラブルの根本原因を突き止め、安定した加工を実現することは困難でしょう。この記事では、そうした経験則を一歩超えるための、科学的根拠に基づいた新たな視点を提供します。なぜ工具が欠けるのか、なぜ面が荒れるのか。そのメカニズムを材料の内部構造から解き明かし、あなたが明日から現場で実践できる具体的な対策と考え方を提示することをお約束します。
表面的な硬度だけで判断は危険!熱処理材の内部構造を考慮する重要性
加工の現場では、ワークの硬さをHRC(ロックウェル硬さ)といった数値で管理することが一般的です。この数値は確かに重要な指標ですが、それだけを信じて加工計画を立てることは、非常に危険な行為と言えます。なぜなら、同じHRC50の鋼材であっても、その内部に広がる金属組織の世界は全く異なる場合があるからです。例えるなら、同じ体重の人でも、一方は筋肉質で、もう一方はそうでないのと同じです。見た目の数値だけでは分からない、材料の「体質」とも言える内部構造を考慮することこそ、熱処理材加工を成功させるための鍵となります。
マルテンサイト、ベイナイト…熱処理で変わる金属組織と被削性の関係
鋼は、熱処理の冷却速度によってその内部組織を劇的に変化させます。この組織の違いが、硬度計の数値には現れない「被削性(削りやすさ)」に決定的な影響を与えるのです。代表的な組織として知られる「マルテンサイト」は非常に硬い一方で脆い性質を持ち、「ベイナイト」はマルテンサイトに次ぐ硬さを持ちながらも粘り強い(靭性が高い)という特徴があります。フライス加工において、この「脆さ」や「粘り強さ」を考慮することは極めて重要です。
| 金属組織 | 特徴 | 被削性への影響と考慮点 |
|---|---|---|
| マルテンサイト | 非常に硬いが、脆い(靭性が低い)。焼入れによって生成される代表的な組織。 | 硬さゆえに切削抵抗は大きいが、脆いため切りくずは分断されやすい。刃先に衝撃が加わるとチッピングしやすいため、刃先の強度を考慮した工具選定が不可欠。 |
| ベイナイト | マルテンサイトに近い硬さを持ちながら、靭性が高い(粘り強い)。 | 粘り強さがあるため、切削時に刃先にまとわりつくような挙動を示すことがある。マルテンサイトに比べ、切削熱が発生しやすく、工具摩耗が進行しやすい傾向にある。 |
| ソルバイト/トルースタイト | 焼戻しによってマルテンサイトが変化した組織。硬さと靭性のバランスが取れている。 | 比較的安定した加工が可能だが、焼戻し温度によって特性が大きく変わるため、熱処理の履歴を正確に把握し、切削条件を考慮する必要がある。 |
硬さのムラはなぜ起きる?不均一性が工具寿命に与える深刻な影響を考慮する
理想的な熱処理とは、ワーク全体が均一に冷却され、狙い通りの組織と硬さになることです。しかし現実には、ワークの形状(厚肉部と薄肉部の差)や冷却方法によって、どうしても冷却速度にムラが生じてしまいます。その結果、ワークの内部には硬い部分(マルテンサイトリッチな領域)と、比較的柔らかい部分(ベイナイトやパーライトが混在する領域)がまだらに存在することになるのです。これが「硬さのムラ」の正体です。工具の刃先は、この硬さの異なる領域を高速で断続的に切削することになり、まるでガタガタ道を高速で走る自動車のように、絶え間ない微細な衝撃を受け続けることになります。この衝撃こそが、工具寿命を著しく縮める「見えない敵」なのです。
熱処理による「内部応力」という時限爆弾を考慮した加工計画とは
焼入れのように、高温状態から急激に冷却される過程で、鋼の内部には非常に大きな「内部応力(残留応力)」が蓄積されます。これは、材料が縮もうとする力と、それを妨げる力が内部で綱引きをしているような状態であり、いわば加工を待ち構える「時限爆弾」のような存在です。この内部応力を考慮せずに加工を進めてしまうと、材料が除去された瞬間に応力のバランスが崩れ、まるで解放されたバネのようにワークが「パッ」と変形してしまうことがあります。これが、高精度な加工を阻害する歪みの原因です。したがって、加工計画を立てる際は、荒加工の段階で意図的に応力を解放させ、その後の変形を見越した取り代を設定するなど、この時限爆弾を安全に処理する工程を組み込む戦略的な視点が不可欠となります。
あなたの常識を覆す!フライス加工における熱処理材の意外な挙動
熱処理材の加工と聞くと、多くの技術者が「硬い材料との力比べ」を想像するかもしれません。しかし、その本質は単なる硬さとの戦いではないのです。熱処理によって鋼の内部で引き起こされる変化は、硬度の上昇だけにとどまりません。それは、熱の伝わり方や切りくずの生まれ方、さらには加工そのものによって材料が自ら硬くなろうとする性質にまで及びます。これらの「意外な挙動」を考慮に入れない限り、いくら高性能な工具を使っても、根本的な問題解決には至らないでしょう。ここでは、あなたの常識を覆すかもしれない、熱処理材が加工中に見せる3つの特異な振る舞いに焦点を当てて解説します。
熱伝導率の低下が引き起こす「切削点の熱暴走」のメカニズム
熱処理が施された鋼材は、まるで断熱材のように熱を伝えにくくなる、という事実をご存知でしょうか。これは、熱処理によって内部の金属組織が緻密なマルテンサイトなどに変化し、熱エネルギーの伝達が阻害されるために起こる現象です。この特性が、フライス加工において「切削点の熱暴走」という深刻な問題を引き起こします。通常の生材であれば、切削によって発生した熱の多くはワーク側へと速やかに拡散していきます。しかし、熱伝導率の低い熱処理材では熱の逃げ場がなく、そのほとんどが工具の刃先という一点に集中してしまうのです。結果として刃先温度は急激に上昇し、工具コーティングの耐熱限界を超えて劣化を招いたり、超硬母材そのものを軟化させたりします。これが、工具摩耗が予測不能な速さで進行するメカニズムです。
なぜ熱処理材は切りくずが繋がりにくい?切りくず処理で考慮すべきこと
焼入れされた高硬度材を加工すると、切りくずが長く繋がらず、まるで砂のように細かく分断される傾向にあります。これは、材料が硬く、そして脆い(もろい)性質を持つためです。粘りのある生材のように塑性変形して繋がっていくのではなく、刃先の前でせん断破壊を起こし、ポロポロと崩れるようにして排出されます。一見すると、切りくずが工具やワークに絡みつかないため、処理が楽なように思えるかもしれません。しかし、ここにも考慮すべき落とし穴が存在します。この硬くて鋭利な微細な切りくずは、加工中のワークと工具の間に噛み込まれ、仕上げ面を傷つける「むしれ」の原因となります。また、機械の摺動面やクーラントタンクに堆積してトラブルを引き起こしたり、エアブローで飛散して作業環境を悪化させたりするリスクも考慮しなければなりません。
加工硬化は敵か味方か?その特性を考慮した切削戦略
「加工硬化」とは、切削加工による圧力や熱によって、ワークの表面層が元の状態よりもさらに硬くなる現象を指します。熱処理材、特に粘り強さ(靭性)を残した調質鋼などは、この加工硬化を起こしやすい性質を持っています。この特性は、加工者にとって厄介な「敵」となり得ます。なぜなら、一度通過した刃道(刃物の軌跡)を次の刃が切削する際、そこはすでに硬化した層に変わってしまっているからです。この硬化層が工具の刃先を激しく摩耗させ、寿命を縮めるのです。しかし、この性質を理解すれば、戦略的に「味方」につけることも可能です。重要なのは、加工硬化層を「撫でる」のではなく、その「下を削る」という意識を持つこと。つまり、加工硬化を恐れて切込み量を極端に減らすのではなく、硬化層の厚さ以上にしっかりと切り込むことで、工具は常に硬化していない新しい面を削ることができるのです。この特性を考慮した切削戦略こそが、熱処理材加工の鍵となります。
工具選定の失敗は9割がコレ!「破壊モード」から逆算する熱処理材への考慮
「高硬度材用」と謳われた高価な工具を使っているのに、なぜかすぐにダメになってしまう。その原因は、工具の性能不足ではなく、あなたの選定プロセスそのものにあるのかもしれません。熱処理材加工における工具選定で最も重要なのは、「なぜ工具が壊れるのか」という破壊のメカニズム、すなわち「破壊モード」を正確に理解することです。工具のトラブルには、刃先が微小に欠ける「チッピング」と、徐々にすり減っていく「摩耗」の二種類が大きく存在します。あなたの現場で起きているトラブルがどちらのタイプなのかを見極め、その原因から逆算して工具の材質や形状を考慮することが、工具選定の失敗をなくすための最短ルートなのです。
チッピング?摩耗?あなたの工具トラブルの原因から最適な材質を見抜く方法
工具の寿命を判断する際、その終わり方が「欠けて終わる」のか「摩耗して終わる」のかを観察することは、次に打つべき手を考える上で極めて重要です。なぜなら、チッピングと摩耗では、その原因と対策が全く異なるからです。チッピングは主に衝撃的な負荷が原因で発生するため、工具母材には「靭性(じんせい:粘り強さ、欠けにくさ)」が求められます。一方、摩耗は熱や摩擦が原因であるため、工具母材には「硬度」や「耐熱性」が重要となります。現在使用している工具のトラブル状況を正しく分析し、それに合った特性を持つ材質を選ぶという視点を持ちましょう。
| 破壊モード | 現象 | 主な原因 | 対策として考慮すべき工具材質の特性 |
|---|---|---|---|
| チッピング | 刃先が微小に「ポロッ」と欠ける。突発的に発生することが多い。 | ・ワークの硬さのムラ ・断続切削による衝撃 ・機械剛性の不足 | 靭性(粘り強さ)を優先する。 硬度は少し低めでも、衝撃に耐えることができる材質を選ぶ。 |
| 摩耗 | 刃先が徐々にすり減っていく。比較的、進行が予測しやすい。 | ・切削熱による刃先の軟化 ・ワークとの化学反応 ・摩擦による物理的な消耗 | 硬度と耐熱性を優先する。 高温下でも硬さを維持できる材質を選ぶ。 |
コーティング選定で考慮すべきは耐熱性か潤滑性か?AlTiN系 vs TiSiN系
熱処理材加工の成否は、工具のコーティングが左右すると言っても過言ではありません。切削時の過酷な環境から超硬母材を保護するコーティングには、様々な種類がありますが、特に重要となるのが「耐熱性」です。切削点が熱暴走しやすい熱処理材加工では、いかに高温下でコーティングの硬度を維持できるかが鍵となります。代表的な耐熱コーティングとしてAlTiN(窒化アルミチタン)系が知られていますが、近年ではそれを上回る性能を持つTiSiN(窒化チタンシリコン)系なども登場しています。自身の加工環境(切削速度、ドライかウェットか等)を考慮し、最適な特性を持つコーティングを選定することが不可欠です。
| コーティング種別 | 特徴 | 得意な加工領域・考慮点 |
|---|---|---|
| AlTiN系 (窒化アルミチタン) | 高温になると表面に硬質で安定した酸化アルミニウム(Al2O3)の保護膜を形成する。高い耐熱性と耐酸化性を持つ、高硬度材加工のスタンダード。 | HRC40~55程度の中高硬度材の高速加工やドライ加工で優れた性能を発揮する。汎用性が高く、まず試すべきコーティングの一つ。 |
| TiSiN系 (窒化チタンシリコン) | AlTiN系を上回る極めて高い硬度と耐熱性を持つ。ナノレベルの結晶構造により、高温下でも硬度低下が少ない。 | HRC60を超える焼入れ鋼など、より高硬度な材料の加工に適している。仕上げ加工で高い面品位を求める場合にも有効。 |
ポジ刃とネガ刃、熱処理材の特性を考慮した使い分けの判断基準
工具の刃先形状、特にすくい角がプラスの「ポジ刃」か、マイナスの「ネガ刃」かという選択は、加工の安定性に直結する重要な要素です。一般的に、ポジ刃は切れ味が鋭く切削抵抗が低い反面、刃先の強度が弱くなります。対してネガ刃は、刃先角度が鈍角になるため強度は格段に向上しますが、切削抵抗は大きくなります。熱処理材を加工する際の基本的な考え方は、「刃先の強度を確保できるネガ刃を優先する」ことです。硬い材料に食い込む際の衝撃や、硬さのムラによる負荷に耐えるためには、刃先の強度が何よりも重要だからです。ただし、機械の剛性が低い場合や、ワークが薄肉でびびりやすい場合には、切削抵抗の低いポジ刃を選択するなど、状況に応じた柔軟な判断が求められます。
CBNは最終手段?超硬工具で挑むための限界と考慮すべき条件
HRC60を超えるような高硬度材の加工において、CBN(立方晶窒化ホウ素)工具はまさに切り札的な存在です。その圧倒的な硬度と耐熱性は、超硬工具では太刀打ちできない領域での加工を可能にします。しかし、CBNは非常に高価であり、安易な導入は工具コストの高騰に直結します。そこで重要になるのが、「どこまで超硬工具で挑むか」という限界の見極めです。近年の超硬工具の進化は目覚ましく、新しい母材やコーティング技術によって、従来はCBNの独壇場だった領域にも対応可能になってきています。まずは、最新の高性能な超硬工具の能力を最大限に引き出す条件(高剛性な機械、最適なホルダー、的確な切削条件)を整えることが先決です。その上で、要求される精度や面品位、あるいは工具寿命がどうしても達成できない場合にのみ、CBNを「最終手段」として検討するという戦略的な視点を考慮すべきでしょう。
切削条件の最適化は「熱と力のマネジメント」- 熱処理材加工で考慮すべき新常識
適切な工具を選び出したとしても、それを使いこなす「切削条件」の設定が伴わなければ、宝の持ち腐れとなってしまいます。熱処理材の加工における切削条件の最適化は、単にカタログの推奨値を入力する作業ではありません。それは、切削点というミクロの世界で繰り広げられる「熱」と「力」の激しい攻防を、巧みに制御する「マネジメント」そのものなのです。これまでの「硬いから速度を落とす」といった単純な発想から脱却し、発生する熱をいかにコントロールし、工具にかかる力をいかに安定させるかという、より戦略的な視点を考慮することが、これからの熱処理材加工における新常識と言えるでしょう。
なぜ切削速度を落とすだけではダメなのか?送りを考慮する積極的理由
トラブルが発生した際、反射的に切削速度を落としてしまうのは、多くの技術者が陥りがちな罠です。確かに、切削速度を下げれば切削熱の発生量は減少します。しかし、それは同時に加工時間を増大させ、工具刃先がワークと接触し続ける時間を不必要に長くしてしまうことを意味します。熱伝導率の低い熱処理材の上を、熱い刃先がゆっくりと撫で続ける…。これでは、工具は熱的ダメージをじわじわと蓄積させ、結果的に寿命を縮めてしまうのです。ここで考慮すべきが「送り」の役割です。切削速度を適切に保ちつつ、一刃あたりの送りをしっかりと確保することは、発生した熱を切りくずと共に素早く加工エリアから排出する「熱の運び屋」として機能させるための積極的な戦略なのです。適度な厚みを持った切りくずは、熱を効率的に持ち去ってくれる、いわば最高の冷却材。送りを考慮することは、熱をマネジメントする上で不可欠な要素となります。
切込み量を考慮した負荷分散テクニック:トロコイド加工の有効性
熱処理材の加工では、工具に加わる負荷をいかに安定させるかが、突発的なチッピングを防ぐ鍵となります。特に、溝加工や側面加工において、工具の径方向の切込み量が急激に変化するような加工パスは、工具にとって最も過酷な状況を生み出します。そこで有効なのが、トロコイド加工に代表される高能率加工の考え方です。この加工法は、工具の径方向の切込み量を小さく保ちながら、渦を巻くような滑らかな軌道で高速に切削を進めるテクニック。これにより、工具とワークの接触角が常に一定に保たれ、切削抵抗の急激な変動が抑制されます。結果として、工具は安定した負荷のもとで切削を続けることができ、発生する熱も工具の広い範囲に分散されるため、熱処理材という難敵に対しても驚くほど安定した長寿命を実現することが可能になるのです。これは、切込み量を考慮した負荷分散の好例と言えるでしょう。
ドライ加工 vs ウェット加工、熱処理材の特性を考慮したクーラント戦略
切削油(クーラント)を使うウェット加工か、使わないドライ加工か。この選択は、熱処理材の加工戦略を大きく左右する重要な分岐点です。一般的にクーラントは「冷却」が主な目的と考えられがちですが、熱処理材加工においては、その使い方が諸刃の剣となることを考慮しなければなりません。高温になった刃先にクーラントがかかることで発生する急激な温度変化は、刃先に微細な亀裂(サーマルクラック)を生じさせ、チッピングの引き金となり得るからです。そのため、状況によってはクーラントを使わないドライ加工や、潤滑を主目的としたオイルミスト加工の方が、工具寿命を延ばす結果に繋がるケースも少なくありません。
| 加工法 | メリット | デメリット・考慮点 | 推奨される状況 |
|---|---|---|---|
| ウェット加工 | ・優れた冷却効果 ・切りくずの排出性向上 ・仕上げ面品位の向上 | ・高温の刃先へのクーラント供給によるサーマルクラック(熱亀裂)のリスク ・クーラントの管理コスト | ・断続切削が少なく、安定した切削が続く仕上げ加工 ・切りくず排出が重要な溝加工やポケット加工 |
| ドライ加工 | ・サーマルクラックのリスクがない ・高温域で性能を発揮するコーティング(AlTiN系など)の能力を最大限に引き出せる ・環境負荷が低い | ・切削熱が刃先に集中しやすい ・切りくずの噛み込みや溶着のリスク ・エアブローによる切りくず飛散対策が必要 | ・耐熱性の高いコーティング工具を用いた高速切削 ・鋳鉄など、切りくずが細かくなる材料の加工 |
| オイルミスト加工 | ・冷却作用を抑え、潤滑作用に特化 ・サーマルクラックのリスクを低減 ・ドライ加工に近い環境で摩擦を低減 | ・専用の供給装置が必要 ・ミストの飛散による作業環境への配慮 | ・ドライとウェットの中間的な選択肢 ・工具寿命と環境負荷のバランスを取りたい場合 |
【実践編】S45C-HからSKD11まで!材質別フライス加工で考慮すべきポイント
これまで熱処理材加工における様々な考慮事項を理論的に解説してきましたが、この章ではいよいよ実践編へと移ります。ひとくちに熱処理材と言っても、その材質によって硬度や靭性、含有される合金元素は千差万別であり、それぞれが特有の「個性」を持っています。S45Cの調質材とSKD11の焼入れ材では、まるで対話する相手を変えるかのように、我々加工者もアプローチを根本から変えなければなりません。ここでは、現場で遭遇する機会の多い代表的な熱処理材を取り上げ、それぞれの材質の特性を考慮した、より具体的で実践的な加工のポイントを解説していきます。
調質鋼(S45C-H, SCM435)加工で特に考慮すべき「靭性」との戦い方
S45CやSCM435といった調質鋼は、焼入れ後に比較的高温で焼戻しを行うことで、硬さ(HRC30~40程度)と靭性(粘り強さ)を両立させている材料です。この「靭性」こそが、加工における最大の難敵となります。粘り気が強いため、切りくずが長く繋がりやすく、工具のすくい面に溶着して「構成刃先」を生成しやすいのです。一度、構成刃先が成長・脱落すると、仕上げ面をむしり取ってしまい面品位が悪化するだけでなく、刃先そのものを巻き込んでチッピングさせる原因にもなります。したがって、調質鋼の加工で考慮すべきは、硬さへの対策以上に、いかにしてこの粘り強さを制し、スムーズな切りくず排出を実現するかという「靭性との戦い」に他なりません。対策としては、すくい角の大きなポジティブな刃先で切れ味を重視し、潤滑性に優れたコーティングを選定して溶着を防ぐことが極めて有効です。
工具鋼(SKD11, SKH51)の高硬度材で失敗しないための初期条件設定
金型などに使用されるSKD11やSKH51といった工具鋼は、HRC60前後に達する高硬度材の代表格です。この領域の加工は、もはや切削というよりも、刃先の硬度と圧力で材料を破壊、つまり「削り砕く」というイメージに近くなります。そのため、少しでも条件設定を誤ると、工具は一瞬で破壊に至ります。高硬度材加工で失敗しないためには、まず安全サイドに立った「初期条件設定」を徹底することが何よりも重要です。いきなり高能率を狙うのではなく、まずは安定して加工を完遂させることを最優先に考えましょう。
- 切削速度:工具メーカーの推奨値がある場合でも、まずはその中央値か、やや低めの領域からスタートする。熱の発生を抑制し、刃先の消耗を穏やかにすることが目的。
- 送り:一刃あたりの送り量(fz)は、極端に少なくすると刃先がワーク表面を滑る「撫で切り」状態となり、加工硬化を助長してしまう。推奨値の下限値を確実に確保し、熱を切りくずとして排出できる厚みを維持する。
- 切込み量:特に径方向の切込み量(ae)は、工具径の5~10%程度と小さく設定する。これにより、工具への衝撃的な負荷を緩和し、切削抵抗を安定させることが可能になる。
これらの初期条件から始め、加工音や切りくずの状態、工具の摩耗状況を注意深く観察しながら、徐々に条件を最適化していくという段階的なアプローチを考慮することが、高硬度材加工を成功させるための鉄則です。
高周波焼入れ材など、表面硬化層の加工で考慮すべき特有の注意点
シャフトの軸受部や歯車の歯面など、部分的に耐摩耗性が求められる部品には、高周波焼入れのように表面のみを硬化させる熱処理が施されます。この種のワークを加工する際に最も考慮すべきは、硬い「硬化層」と、元の硬さのままである「母材」が混在しているという、材料の極端な不均一性です。特に、硬化層と母材の「境界」部分を切削する際は、工具の刃先が硬い層と柔らかい層を断続的に出入りすることになり、極めて大きな衝撃負荷を受けます。この負荷変動が、チッピングやびびり振動の直接的な原因となるのです。対策の鍵は、この「境界」をいかに攻略するかにかかっています。可能であれば、硬化層の深さを事前に正確に把握し、一度の切込みで硬化層を完全に通過して母材まで到達させるのが理想です。また、避けられない断続切削となるため、工具材質は硬度よりも靭性を重視した選定が求められます。表面だけを見て判断せず、内部構造の不均一性を常に念頭に置いた加工計画を立てることが不可欠です。
トラブル発生!その時どうする?原因から対策を導く熱処理材の考慮事項
万全の準備を整え、最適な工具と切削条件で加工に臨んだとしても、熱処理材という難敵は時として我々の予測を超えた挙動を見せます。しかし、予期せぬトラブルが発生した際に、闇雲に対策を講じることほど非効率なことはありません。重要なのは、パニックにならずに現象を冷静に観察し、その原因を論理的に特定していくプロセスです。これまで解説してきた熱処理材の特性に関する知識は、まさにこのトラブルシューティングの局面で真価を発揮します。目の前で起きている現象は、必ず何らかの原因から生じている必然の結果。その因果関係を解き明かすための考慮事項を、ここで具体的に見ていきましょう。
異常な工具摩耗が発生した際に真っ先に考慮すべきチェックリスト
「想定よりも工具の寿命が明らかに短い」「特定の工具だけが異常な速さで摩耗する」。このような状況に直面した時、やみくもに切削速度を落とす前に、立ち止まって原因を分析する必要があります。異常摩耗は、熱処理材からの悲鳴であり、加工プロセスにおける何らかのミスマッチを知らせる重要なサインなのです。このサインを正しく読み解くため、以下のチェックリストに沿って多角的な視点から状況を考慮し、真の原因へと迫ることが不可欠です。一つ一つの項目を丁寧に確認していくことで、これまで見えなかった問題の本質が浮かび上がってくるはずです。
| チェック項目 | 確認すべきポイント | 考えられる原因と対策の方向性 |
|---|---|---|
| 1. 工具の摩耗形態 | 刃先の逃げ面が摩耗しているか?すくい面がえぐれるように摩耗しているか?刃先全体が丸まっているか? | 逃げ面摩耗が激しい場合は切削速度が速すぎる可能性。すくい面のクレータ摩耗は熱と化学反応が主因。コーティングの耐熱性や潤滑性を見直す必要がある。 |
| 2. 切りくずの状態 | 切りくずの色は変色していないか(青、紫など)?形状は正常か?粉状になっていないか? | 切りくずの変色は切削点が高温になっている証拠。熱暴走の危険信号であり、切削速度の見直しやクーラント戦略の再考が必要。 |
| 3. 切削音 | 甲高い異音(びびり音)は発生していないか?加工中に音が変化していないか? | 異音はびびり振動や工具のチッピングの兆候。機械やホルダーの剛性、切削条件のバランスが崩れている可能性を考慮する。 |
| 4. 加工面の状態 | 仕上げ面にむしれや白曇りは発生していないか? | 構成刃先の発生や、工具摩耗の末期状態を示唆している。切れ味の良い工具への変更や、潤滑性の高いクーラントの使用を検討する。 |
| 5. 切削条件の再確認 | 一刃あたりの送りは適切か?(撫で切りになっていないか)径方向の切込みは大きすぎないか? | 送りが低すぎると加工硬化を助長し摩耗を促進する。適切な切りくず厚さを確保できているか、再度計算し直す。 |
「びびり」を抑えるための機械剛性と切削条件のバランス調整
甲高い音と共に加工面にウロコ状の模様を残す「びびり振動」は、熱処理材加工において最も避けたいトラブルの一つです。びびりは、工具やワーク、機械が一体となって起こす自励振動であり、一度発生すると工具のチッピングや加工精度の悪化を招くだけでなく、機械本体にもダメージを与えかねません。このびびりを抑えるためには、「機械や保持具の剛性」と「切削条件」という二つの側面からバランスを調整するという視点を考慮することが重要です。多くの場合、まずは切削条件の調整からアプローチします。びびりが発生しにくい「安定領域」を探すため、切削速度を大胆に上下させてみることが有効な場合があります。また、一刃あたりの送りを調整して切削抵抗を変化させることも効果的です。それでも改善しない場合は、工具の突き出し長を可能な限り短くする、より剛性の高いツールホルダーに変更するなど、びびりの源を断つための物理的な剛性向上策を講じる必要があります。
仕上げ面のむしれ・白曇り…面品位を向上させるための最終手段とは?
寸法精度は出ているものの、仕上げ面の見た目が要求品質を満たさない。これもまた、熱処理材加工で頻繁に遭遇する悩みです。代表的なものが、まるで表面をむしり取ったかのような「むしれ」や、艶がなく白っぽく曇って見える「白曇り」です。これらの現象は、工具の摩耗末期に現れることもありますが、多くは切削条件と工具の相性に起因します。「むしれ」は、刃先の切れ味が低下し、材料を「切る」のではなく「引きちぎる」ようになると発生しやすくなります。対策としては、すくい角が大きく切れ味の鋭いポジ刃の工具や、潤滑性に優れたコーティングを選定することが有効です。一方、「白曇り」は切削熱による表面組織の微細な変質が原因の一つと考えられています。これらの対策を講じても改善が見られない場合の最終手段として、刃先に特殊なR形状を持つ「ワイパーチップ」の使用を考慮する価値があります。これは、通常の刃で切削した面を、後続する平坦なワイパー刃が滑らかに「アイロンがけ」するように仕上げることで、劇的に面品位を向上させる効果が期待できます。
そのセッティングで大丈夫?機械剛性と保持具が熱処理材加工に与える影響の考慮
最高の性能を誇る工具を手に入れ、完璧な切削条件をプログラムしたとしても、それだけでは熱処理材という強敵を攻略することはできません。なぜなら、その工具と条件の性能を100%引き出すためには、それを支える揺るぎない「土台」が不可欠だからです。その土台とは、機械本体の剛性であり、工具を掴むツールホルダーであり、ワークを固定するクランプです。これらの要素は、加工の主役である工具の陰に隠れがちですが、実際には加工品質や工具寿命を根底から左右する極めて重要な役割を担っています。熱処理材の硬さに負けない力強い加工を実現するためには、これらの縁の下の力持ちがいかに重要であるかを深く考慮する必要があるのです。
なぜ高剛性マシンが有利なのか?熱処理材加工における影響を考慮する
「熱処理材の加工には、剛性の高い機械が良い」。これは加工現場の共通認識ですが、その理由を深く掘り下げて考えることが重要です。高剛性マシンが有利な理由は、単に「頑丈だから」という単純なものではありません。第一に、熱処理材の切削時に発生する大きな抵抗力に対し、機械構造のたわみや変形を最小限に抑えることができます。これにより、プログラム通りの正確な工具軌道が実現され、高い寸法精度が維持されるのです。第二に、びびり振動の発生を根本的に抑制します。機械全体の剛性が高ければ、振動が発生しにくく、また発生しても速やかに減衰させることができます。振動が少ないという事実は、工具刃先への衝撃的な負荷を劇的に低減させ、突発的なチッピングを防ぎ、結果として工具寿命の安定と延長に直結します。つまり、高剛性マシンへの投資は、部品の品質向上だけでなく、工具費の削減という形で明確なリターンをもたらす戦略的な選択と言えるのです。
ワーククランプ方法で加工精度は変わる!歪みを考慮した固定方法
見落とされがちですが、ワークを固定する「クランプ」の方法は、最終的な加工精度に絶大な影響を与えます。特に、内部に応力を溜め込んでいる熱処理材の場合、その考慮はより一層重要になります。例えば、油圧バイスで過大な力でワークを締め付けたとします。その力によってワークは目に見えないレベルで歪み、その歪んだ状態で加工が進められます。そして加工が終わり、クランプを解放した瞬間、抑えつけられていたワークは元の形に戻ろうとし、結果として加工面に歪みやねじれが生じてしまうのです。これを防ぐためには、必要最小限の力で、かつ均等にワークを固定する技術が求められます。トルクレンチを用いて締め付け力を管理したり、複数のクランプを用いて力を分散させたり、あるいは荒加工と仕上げ加工でクランプする箇所や方法を変えたりするなど、内部応力の解放による変形を常に考慮した戦略的なクランプ計画が、高精度加工を実現する鍵となります。
見落としがちなツールホルダーの重要性:焼きばめか、強力チャックか?
主軸とエンドミルを繋ぐツールホルダーは、単なる「つなぎ役」ではありません。主軸の回転力と剛性をロスなく刃先に伝えるための、極めて重要なコンポーネントです。熱処理材加工のように大きな負荷がかかる状況では、ホルダーの把握力や振れ精度、剛性が工具のパフォーマンスを直接的に左右します。特に高硬度材加工で一般的に用いられるのが、「焼きばめホルダー」と「ミーリングチャック(強力チャック)」です。どちらも優れた性能を持ちますが、その特性には違いがあり、加工内容に応じて使い分けるという視点を考慮すべきです。
| ホルダーの種類 | 特徴 | メリット | デメリット・考慮点 | 熱処理材加工での推奨用途 |
|---|---|---|---|---|
| 焼きばめホルダー | ホルダーを加熱して穴を膨張させ、工具を挿入。冷却による収縮で強力に把握する。 | ・部品点数がなく一体構造のため、極めて高い剛性とバランス性能 ・最高の振れ精度(3µm以下) ・先端部がスリムで、狭所へのアクセス性が良い | ・工具の着脱に専用の加熱装置が必要 ・把握径の範囲が狭い | HRC60を超える高硬度材の仕上げ加工。びびりを徹底的に抑制し、最高の面品位を狙う場合に最適。 |
| ミーリングチャック (強力チャック) | ニードルベアリング(ころ軸受)を介して、レンチ一本で強力かつ均等な把握力を得る構造。 | ・非常に高い把握力と剛性 ・優れた防振性能 ・工具の着脱が容易 | ・構造が複雑でホルダー自体が重く、外径が大きい ・焼きばめに比べると振れ精度はやや劣る | 調質鋼などの重切削、荒加工。大きな切削抵抗に負けない安定した加工を実現したい場合に最適。 |
| ERコレットチャック | コレットナットを締め込むことで、スリットの入ったコレットが工具を把握する。 | ・汎用性が高く、様々な径の工具に対応可能 ・比較的安価 | ・把握力、剛性、振れ精度の全てにおいて上記2種に劣る | 熱処理材の加工、特に荒~中仕上げにおいては推奨されない。負荷の少ない軽切削や穴あけなどに用途が限定される。 |
加工現場のヒーローになる!前後工程まで考慮した熱処理材の段取り術
これまでの議論は、まさに工具がワークに切り込んでいる瞬間の、ミクロな世界に焦点を当ててきました。しかし、真に優れた加工技術者とは、自分の持ち場であるフライス加工だけを見るのではなく、その前後の工程、つまり「熱処理」そのものや、熱処理後の「仕上げ」までを見通す広い視野を持っています。熱処理材の加工は、単独の工程で完結するものではありません。前工程からバトンを受け取り、次工程へとスムーズに繋ぐための戦略的な「段取り」こそが、加工現場のヒーローとなるための条件と言えるでしょう。この章では、そのための具体的な考慮点について深く掘り下げていきます。
熱処理の歪みを考慮した「前加工での取り代」の賢い設定方法
熱処理、特に焼入れを行うと、ワークは程度の差こそあれ必ず「歪み(ひずみ)」や「変形」を起こします。これは、急激な加熱冷却によって内部組織が変化し、体積が膨張・収縮するために避けられない物理現象です。この事実を無視して、熱処理前の加工でギリギリの寸法まで追い込んでしまうと、歪みによって仕上げ代が不足し、最悪の場合、製品として成立しなくなってしまいます。したがって、熱処理前の加工で最も考慮すべきは、この予測される歪み量を見越した、適切な「取り代(とりしろ)」を設定することです。取り代が少なすぎれば不良品のリスクが高まり、逆に多すぎれば後工程である仕上げ加工の負担が増大し、コストアップに直結します。過去の類似形状のワークにおける歪みデータを蓄積・分析したり、非対称な形状や肉厚が大きく異なる部分の変形を予測したりするなど、経験とデータに基づいた賢い取り代設定が、前後工程を繋ぐ重要な鍵となるのです。
仕上げは研削?それとも高硬度ミーリング?コストと精度を考慮した工程設計
熱処理後の高硬度なワークを最終的な寸法・面品位に仕上げる工程には、大きく分けて「研削加工」と「高硬度ミーリング(フライス加工)」の二つの選択肢が存在します。かつては熱処理後の仕上げといえば研削が常識でしたが、近年の工具技術や機械性能の向上により、高硬度ミーリングも非常に有力な選択肢となっています。どちらの加工法を選択するかは、要求される精度、コスト、納期、そして設備の状況などを総合的に考慮した、戦略的な工程設計が求められます。単純な優劣ではなく、それぞれの特性を理解し、製品にとって最適な方法を見極める視点が不可欠です。
| 加工法 | メリット | デメリット | 考慮すべき選択基準 |
|---|---|---|---|
| 研削加工 | ・極めて高い寸法精度と優れた面粗度が得られる。 ・安定した品質を確保しやすい。 | ・専用の研削盤が必要。 ・砥石のドレッシングなど、段取りに時間がかかる。 ・加工能率はミーリングに劣る傾向がある。 | サブミクロン単位の超高精度が要求される場合や、鏡面のような仕上げ面が必要な場合に最適。 |
| 高硬度ミーリング | ・マシニングセンタ一台で荒加工から仕上げまで完結できる。 ・複雑な三次元形状の加工も可能。 ・段取り時間が短く、加工能率が高い。 | ・研削に比べると、最高到達精度や面粗度で一歩譲る場合がある。 ・工具や機械への負荷が大きく、安定した加工には高い技術が求められる。 | コストとリードタイムを重視する場合や、自由曲面を含む金型などの加工で大きな強みを発揮する。 |
熱処理業者との連携で変わる!加工者が伝えるべき重要情報とは
多くの加工現場では、熱処理を専門の外部業者へ委託しています。この時、加工者と熱処理業者の間で十分なコミュニケーションが取れていないと、思わぬ品質問題に繋がることがあります。熱処理業者は、図面に書かれた材質と硬度の指示に従って処理を行いますが、その部品が後工程でどのように加工され、どの面が重要になるかまでは分かりません。そこで重要になるのが、加工者側からの積極的な情報提供です。単に「HRC60でお願いします」と依頼するだけでなく、加工の都合を考慮した付加情報を伝えることで、熱処理の品質は格段に向上し、後工程の加工を劇的に楽にすることができるのです。良好なパートナーシップを築くことは、高品質なものづくりに欠かせない要素と言えるでしょう。
| 加工者が伝えるべき重要情報 | その理由と期待される効果 |
|---|---|
| 最終的な加工の基準面 | 熱処理業者は、その面を基準にワークを炉に置いたり、歪み測定を行ったりできるため、処理精度が向上する。 |
| 特に高い精度が要求される箇所 | その部分の歪みが最小限になるような置き方や冷却方法を考慮してもらえる可能性がある。 |
| 歪みを特に嫌う方向 | 長尺物であれば長手方向の反り、薄板物であれば平面の歪みなど、特に避けたい変形を伝えることで、適切な処置(歪み取りなど)を促せる。 |
| 前加工での取り代の情報 | どの程度の仕上げ代が残っているかを伝えることで、表面の脱炭層などを考慮した熱処理が可能になる。 |
コストダウンと品質向上を両立する、戦略的な熱処理材加工への考慮
これまで、熱処理材加工における様々な技術的な側面を解説してきました。最終章となるこのセクションでは、視点を一段引き上げ、コストと品質という経営的な観点から、戦略的なアプローチを考えていきます。「熱処理材の加工は、コストがかかって当たり前」という固定観念は、もはや過去のものです。最新の工具、革新的な加工方法、そしてこれまで培ってきた知識を戦略的に組み合わせることで、コストダウンと品質向上という、一見すると相反する二つの目標を同時に達成することが可能になります。守りの姿勢から脱却し、付加価値を生み出す「攻め」の加工へと転換するための考慮点を、具体的に見ていきましょう。
工具費はコストか投資か?工具寿命と加工能率から考える損益分岐点
高性能なコーティングが施された最新の超硬エンドミルは、確かに高価です。その価格だけを見て、「うちでは使えない」と判断してしまうのは、非常にもったいない決断かもしれません。ここで考慮すべきは、工具費を単なる「コスト(費用)」として捉えるのではなく、生産性を向上させるための「投資」として捉える視点です。例えば、一本1万円の工具Aが1時間で寿命を迎えるのに対し、一本3万円の工具Bが加工能率を2倍に高め、さらに5時間使えるとしたらどうでしょうか。機械の稼働コスト(チャージ)が1時間5000円だと仮定すれば、トータルコストで見た場合の優位性は明らかです。目先の工具価格に惑わされることなく、加工時間の短縮による機械チャージの削減や、工具交換回数の減少による段取り時間の削減といった、トータルでの損益分岐点を考慮することが、真のコストダウンへの第一歩となります。
サイクルタイム短縮のために、まず考慮すべきボトルネック工程の特定
一つの製品を完成させるまでの一連の工程時間、すなわちサイクルタイムを短縮することは、生産性向上の最も直接的な手段です。しかし、やみくもに全体のスピードアップを図ろうとしても、効果は限定的です。重要なのは、全体の流れの中で最も時間がかかっている工程、いわゆる「ボトルネック」を正確に特定し、そこに改善リソースを集中投下することです。熱処理材のフライス加工においては、そのボトルネックは製品の形状や要求品質によって様々です。除去する体積の大きい荒加工が律速段階になっているのか、あるいは高精度が求められる仕上げ加工に延々と時間を費やしているのか。まずは、各工程の時間をストップウォッチで計測するなどして現状を正確に把握し、どこに最も改善の余地があるのかを考慮することが、効果的なサイクルタイム短縮の鍵を握っています。
AIによる加工条件最適化はどこまで可能か?未来の熱処理材加工を展望する
熱処理材の加工は、これまで熟練技術者の経験と勘に頼る部分が非常に大きい領域でした。しかし、その“暗黙知”の世界にも、デジタルトランスフォーメーションの波が押し寄せています。近年、AI(人工知能)やシミュレーション技術を活用し、複雑で予測困難なこの領域に科学的なアプローチで挑む動きが加速しています。CAMソフトウェアに搭載されたAIが、工具やワークの形状から最適な加工パスと切削条件を自動で算出したり、加工前に熱処理による歪みや切削抵抗をシミュレーションで予測したりする技術は、すでに実用化の段階に入りつつあります。
もちろん、これらの技術が熟練者の全てに取って代わるわけではありませんが、技術者の判断を支援し、試行錯誤の時間を大幅に短縮してくれる強力なツールとなることは間違いないでしょう。未来の熱処理材加工は、人間の創造性とAIの解析能力が融合した、より高度で知的な領域へと進化していくはずです。
- AIによる切削条件の自動生成:工具、材質、機械の情報を基に、最適な切削速度や送りをAIが提案する。
- シミュレーションによる事前検証:加工前にPC上で切削シミュレーションを行い、びびりの発生や工具負荷を予測・回避する。
- デジタルツインの活用:現実の機械と双子(ツイン)となるデジタル空間上のモデルで加工を再現し、プロセスの最適化を図る。
- センシング技術との連携:加工中の振動や音、熱をセンサーで監視し、リアルタイムで条件をフィードバック制御する。
まとめ
フライス加工における熱処理材との向き合い方、その探求の旅路もいよいよ終着点です。この記事を通じて、当初「硬いから難しい」という一言で片付けていた問題が、いかに奥深く、多面的な要因によって引き起こされていたかをご理解いただけたのではないでしょうか。それはまるで、未知の惑星を探査するかのように、材料の内部構造から熱や力の挙動、そして機械や人との関わりに至るまで、一つ一つの現象を丁寧に読み解く冒険でした。
工具の破壊モードから逆算する選定法、熱と力をマネジメントする切削条件の最適化、そして前後工程までも見据えた戦略的な段取り術。これらは単なる個別のテクニックではありません。熱処理材の考慮とは、単なる技術的対策の積み重ねではなく、材料との対話を試み、その声に耳を傾けるという、ものづくりの根源的な姿勢そのものなのです。この視点こそが、日々のトラブルを回避し、コストダウンと品質向上を両立させるための羅針盤となります。
この記事で手にした知識は、明日からのあなたの現場を確実に変える力となるでしょう。しかし、理論と実践の間には、時に予期せぬ壁が立ちはだかるもの。もし、あなたが向き合っているその難題について、あるいは長年苦楽を共にしてきた工作機械について、さらなる一歩を踏み出すための具体的な相談が必要だと感じたなら、いつでも私たちにお声がけください。あなたの挑戦が、新たな価値を創造する未来へと繋がる旅は、まだ始まったばかりです。
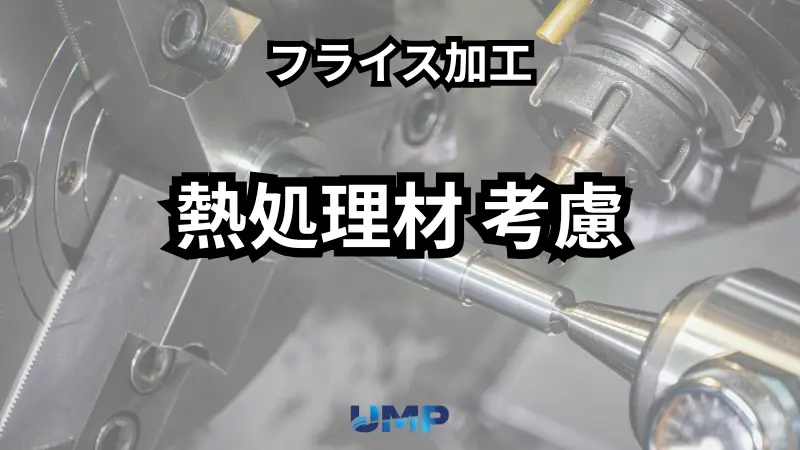
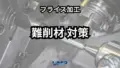
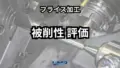
コメント